『311』というタイトルの映画に賛否 被災者にカメラを向け「自分がハイエナのような自覚がありました」と監督が吐露
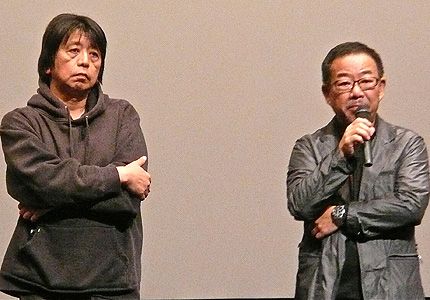
森達也、綿井健陽、松林要樹、安岡卓治の気鋭ドキュメンタリスト4人が共同監督を務めたドキュメンタリー『311』が9日、山形国際ドキュメンタリー映画祭2011で上映され、その内容を巡って物議を醸している。
同作品は東日本大震災の2週間後、福島から岩手県陸前高田・大船渡、そして児童の8割が死亡・行方不明となった宮城・石巻市立大川小学校など被災地を巡るもの。もともと映画化の予定はなく被災地を現認することが目的だったため、カメラは4人の素の姿を写し出す。無防備に車で福島を目指した4人だったが、福島第一原子力発電所に近づくにつれてガイガーガウンターの放射線測定値がグングン上がり、うろたえ、悪ふざけして恐怖を紛らわせようとする。津波で壊滅的な被害を受けた陸前高田の街並みを目にした時は、あまりの惨劇に言葉を無くした。そして行方不明の家族を探している被災者に話しを聞こうにも、声をかけるきっかけすらうまく掴めない。森はオウム真理教事件を、綿井はイラクの戦火を、松林は『花と兵隊』でタイ・ビルマの未帰還兵を、そして安岡は原一男監督『ゆきゆきて、神軍』の助監督を務めるなど数々の修羅場をくぐってきた4人だが、為す術もなく、ぶざまな姿を晒す。彼らを通して改めて震災被害の甚大さを思い知る内容となっている。
釜山国際映画祭でのワールドプレミア後、すぐに山形入りした森は「震災後は強烈なうつ状態になっていて何をする気にもなれず、被災地のニュース映像を見ては涙を流している日々だった。そんな最中、綿井さんから被災地行きに誘われ一度は断ったが、東京にいて擬似的PTSD(心的外傷後ストレス障害)になっているのなら現地へ、せっかく行くなからカメラを持っていった。しかし、実際に被災地の凄まじさに圧倒され、気づいたらカメラを回し始めていた。極めてエゴイスティックな理由で撮影した記録です」と本作に関わった理由を説明した。続いて安岡も「最初はこれで映画を作る意識はなかったが、しかし現地を訪れた1週間の間で、森さんがどんどん先鋒に(被災者に対して)切り開いて行ったので、(作品として)ある形を提示出来るのではないか?と思った。震災ではマスメディアの活発な報道があったが、被災者の現状や苦しみを伝える報道は飽和しているんじゃないかと思うくらい溢れていた。その中で見落とされたモノは何か? 撮り手である私達が被災者と出会って変化していく姿を見せることで、報道の在り方など提示することが出来ると思った」と製作意図を語った。
しかし上映後の質疑応答で、地震により自宅が半壊したという仙台の女性から「『311』というタイトルがついているが、扱っているのは津波と原発のみで、震災がもたらした被害はそれだけではないと思う。しかもマスメディアがすでにカメラを向けた同じ場所にしか(関心を)向けていないのではないか」と痛烈に批判した。これには森も「おっしゃる通りだと思います。その見方で正解です」と恐縮しきり。松林も「この映画だけでは311を捕らえきれてないと思います。なので僕は、この後すぐに福島に入り『相馬看花-第一部 江井部落-』を撮り、今も追い続けています」と弁明した。
また映画後半には遺体にカメラを向けたことから、遺族に木の棒を投げつけられ、罵られるシーンもある。そのために上映後のロビーでは監督たちに「遺族があそこまで怒っているのに、そのシーンを入れるとは!」と詰め寄る男性もいた。
その後行われた「震災と向き合って」と題したシンポジウムで、安岡は「確かに僕らは遺体が配送される場所の情報を聞いてその映像を撮ろうと待っていた。自分がハイエナのような自覚がありました」と心情を吐露した。森も「あれだけの規模の震災を前に何を撮って何を伝えるべきか、僕自身も分からなくなってしまった。それはメディアの人間が共通で抱えていた心だと思う。この気持ちを誤魔化したくないし、それを安岡さんが編集したこの映画で追体験した。被災者の方には申し訳ないが、これは自分の中の業と後ろめたさを見つめる旅だったと思う。なので、遺族の方に怒鳴られてホッとしたし、そのシーンを入れることで落とし前をつけたような気分になったのは確かです」と胸の内を明かした。
本作は今後、劇場公開が予定されているが、震災報道を巡るマスメディアの対応について問題提起するだけでなく、作品そのものも賛否両論を呼びそうだ。(取材・文:中山治美)


