ミルクマン斉藤:映画短評の著者

略歴
映画評論家。1963年京都生まれ。デザイン集団「groovisions」の、唯一デザインしないメンバー。現在、京都・東洞院蛸薬師下ルの「三三屋」でほぼ月イチ・トークライヴ「ミルクマン斉藤のすごい映画めんどくさい映画」を開催中。雑誌「テレビブロス」「ミーツ・リージョナル」「キネマ旬報」等で映画コラムを連載中。
リンク
映画短評一覧

首
景気よく首が飛びまくります。

サタデー・フィクション
キモとなるのは横光利一の小説「上海」。

ゴジラ-1.0
ゴジラ史上、一、二を争う傑作。

ポッド・ジェネレーション
風刺的コメディぽくもあるが笑えない。

ペルリンプスと秘密の森
想像を刺激するファンタジーSF。

怪物の木こり
あの絵本は実際に出版して欲しいなあ。

春の画 SHUNGA
森山未來、吉田羊のナレーションも良い。

愛にイナズマ
タイトルの真意は最後にやってくる。

おまえの罪を自白しろ
やはり監督には向いてるものと、じゃないのとがある。

リバイバル69 ~伝説のロックフェス~
先人へのオマージュに満ちたロックンロール映画。

アントニオ猪木をさがして
誰も見つけられない猪木という巨人の存在。

キリエのうた
「憐れみの賛歌」という名を持つ女性に幸あれ。

唄う六人の女
思いっきり観るものを惑わせ狂わせてくれます。

春画先生
心のリミッターを外される/外すことの快感。

クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル トラヴェリン・バンド
ジェフ・ブリッジスがナレーション、っていかにも。
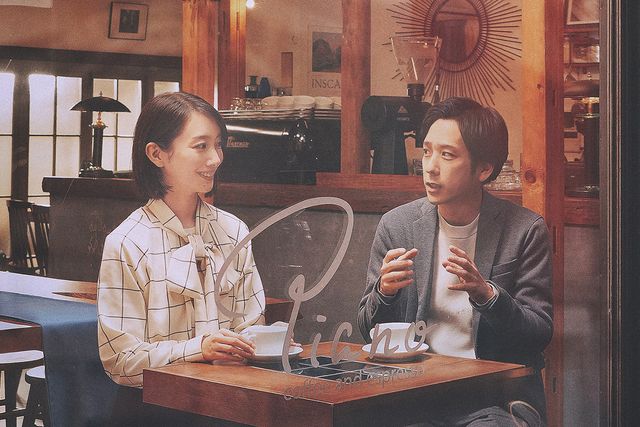
アナログ
涙の一滴も出ないけれども…。

オオカミの家
見てはいけないものを見てしまったトラウマ感。

キリング・オブ・ケネス・チェンバレン
切実さはびんびん伝わってくるものの。

シアター・キャンプ
愛情に溢れたほんわかミュージカル劇。

ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家(シネアスト)
世を去ってなお謎と矛盾に満ちた知性を追う。


