『KOKORO』國村隼 単独インタビュー
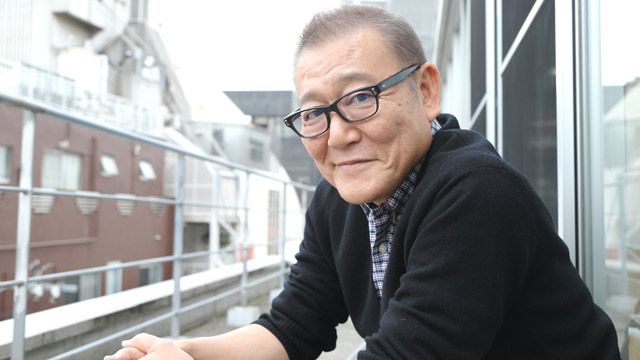
映画のスキルを学んだのは海外だった
取材・文:くれい響 写真:高野広美
日本のある小さな村を舞台に、“最愛の弟の死”という深い傷を心に負ったフランス人女性・アリスの姿を追った映画『KOKORO』。ベルギーの女性監督ヴァンニャ・ダルカンタラが描く再生物語で、イザベル・カレ演じるヒロインに優しく寄り添う元警官のダイスケを演じるのが國村隼だ。これまでアジアやハリウッドなど、さまざまな国の作品に出演してきた彼が隠岐島での撮影や作品の深いテーマ性、さらに合作における心構えなどについても語った。
世界には特別に「映画に関わる人種」が存在する

Q:韓国映画『哭声/コクソン』に続き、本作はベルギー=フランス=カナダ合作ですが、海外の方と映画を制作することに関して、どのように思われますか?
今回は肉体的に大変だった『哭声/コクソン』の現場から戻ってきた後にオファーをもらいました。日本のプロダクションだけじゃなく、海外のプロダクションと一緒に映画を制作するのは、僕のキャリアでいうと割と普通のことなんですよ。デビュー2作目がハリウッド映画の『ブラック・レイン』で、その後は香港映画で5、6本やっていますし。つまり自分の中で映画のスキルを教えていただいたのがそこなので、違和感みたいなものはないんです。
Q:役者として撮影現場でやることは、どの国の作品でも変わらないと?
そうですね。国籍も言語も違いますが、世界には特別に「映画に関わる人種」が存在するのかと思ってしまうぐらい、どこかでわかり合うことができる。ただ、状況が違うというのはあります。『哭声』ではとんでもない山奥での撮影でしたし、監督がどれだけ我が意を通そうとするかとかもあります。でも、それも監督のスタイルだと思えば、そこまで大変とは思いませんよ(笑)。『ブラック・レイン』のときに強く教えてもらったのは、我々役者は映像を完成させるためのパーツを作っている、材料集めをしているということですね。
Q:ちなみに本作は、海外ロケに参加するのではなく、日本ロケに海外のスタッフや俳優を迎え入れるかたちでしたが、特に心構えのようなものは?
主演のイザベル(・カレ)がフランスの役者さんで、監督のヴァンニャ(・ダルカンタラ)がベルギー人。関わっている人間の半分ぐらいが日本国籍じゃない程度で、映画の現場に必要なクリエイターは全部そろっていました。だから何の違和感もないし、僕に関しても彼らを迎え入れるという、ホスト的な気持ちは特になかったです。僕自身、(ロケ地である)隠岐島に来て、「日本にこんなところがあるんだ!」とビックリしたぐらいですから(笑)。
キャラをイメージすることは、デッサンと同じ

Q:今回演じられたダイスケは実在する人物がモデルになっていますが、どのような役づくりをされましたか?
彼を知る人からお話を聞いた程度で、監督が書いた脚本を読んだときに感じた自分の中にあるダイスケのイメージを下敷きにしながら膨らませていきました。彼は自殺志願者を助けているように見えながら、じつはその行為を通して、“生きていくこと”について学んだり、助けられてもいるんじゃないかと。僕の場合、役をイメージすることは、画を描くうえでのデッサンみたいなもの。現場で作業していくことで、構図をハッキリさせ、色付けしていくんです。
Q:ちなみに、撮影現場の雰囲気はいかがでしたか?
現場は監督の持っている人柄みたいなものが色濃く反映されるものですが、この作品もヴァンニャの人柄そのままを反映したような、穏やかな雰囲気で、殺伐とした感じは一切ありませんでした。特に急いでいるわけでも、バタバタしてるわけもなく、自然に水が流れるかのごとくスムーズに作業が進んでいました。それは仕上がった作品にも反映されているかと思います。
Q:完成した作品をご覧になっての感想があれば教えてください。
撮影をヨーロッパで超一流のカメラマンである、ルーベン・インペンスが担当しているんですが、彼が現場で使っていた軽量のステディカムの効果が、見事なまでによく出ていましたね。自然光を多く生かした映像の美しさは、この作品では大きなウエイトを占めますから。また、どの映画でも、お箸の使い方など食卓シーンを観れば、どんな家庭かすべてわかると思うんですが、今回もなかなか不思議な食卓シーンになったと思いますね。
忘れかけていた心を思い出す風景

Q:ちなみに、モデルとなった男性のドキュメンタリー映画もフランス人監督によって制作されていますが、彼らがこの題材に惹かれる理由は何だと思いますか?
彼らが惹かれる理由が、まさに『KOKORO』という作品に流れているテーマそのものだと思うんです。この映画を観てもらったときに、イザベルが演じたヒロイン・アリスを通して、それが答えになっているんじゃないかと。「心」という日本語をわざわざアルファベットで表記しているインターナショナルなタイトル自体が、それを表しているような気もします。
Q:隠岐島ロケでの想い出があれば教えてください。
隠岐島には1か月ほど滞在していたのですが、日本人である僕ですら忘れてかけていた、これこそが日本人の心だというようなものを感じました。原日本というものを考えさせられる土地柄だったといえます。地元の方には非常に快く受け入れていただき、いい想い出になりました。麺類が好きな僕にとっては、とにかくおそばが美味しかったですしね、隠岐牛も美味しかったですよ。
Q:本作を、我々日本人はどのように観て、感じたらいいと思われますか?
イザベルが演じたアリスは、一見何の過不足もなく生活をしているように見えますが、自分が無自覚なうちに、澱(オリ)のようにストレスが溜まっているんです。それは日本で暮らしている我々も一緒で、心の中に溜まるオリに対して不感症になっているというか、知らないうちに身体を蝕まれているんじゃないかと。アリスにとっての(日本という)未知の場所に行って、新しい扉を開けようとするのを追体験する気持ちで、あまり理屈で考えずに感じてほしいですね。
知らずに溜まったオリをメンテナンスする物語

Q:つまり、自殺など、ヘビーな題材にあまり引っ張られない方がいいということですね?
そうですね。僕は死云々というものより、異文化の溶け合いを通して、日常生活にある知らず知らずに溜まる自分のオリをメンテナンスして「生きていく」というお話だと思っています。だから、この映画を観ることで、いっぺん立ち止まって、自分に目を向けて検証してみることで、「自分自身の“心”とは一体何か?」ということを考えるのもいいかもしれません。
Q:最後に、これまでのさまざまな経験から、海外のスタッフ、キャストと上手くやっていく、いちばんの方法があれば教えてください。
ひとつだけ挙げるとすれば、現場の状況次第では「YES」「NO」をハッキリ言うべきだということ。自分も含め、日本人って引っ込み思案だったり、ハッキリ言えないことが多いですし、相手次第では「郷に入っては郷に従え」では成り立たないこともありますから。これは自分たちの立場を守るためでもあるし、そうした方が制作もスムーズに進むんです。でも、『KOKORO』では、そんなことを言う必要は、まったくありませんでしたね(笑)。

「俳優の仕事は材料集め」など、今や日本を代表する名俳優がユーモアたっぷりに語る、独自の俳優論には頷くばかり。ちなみに、『KOKORO』撮影後には、中国=香港合作の超大作『追捕 MANHUNT(原題)』にも出演。『ハード・ボイルド/新・男たちの挽歌』以来、四半世紀ぶりとなったジョン・ウー監督作への出演だっただけに、福山雅治らを相手に最凶の悪役を、昔を懐かしみつつ楽しみながら演じたようだ。
(C) Need Productions / Blue Monday Productions
映画『KOKORO』は全国公開中








