第32回
今月の5つ星

深夜テレビドラマに続いて、第2のモテ期を迎えた三十路草食系男子のリアル恋愛ゲームを描いた『モテキ』、エイリアンと人類の攻防を圧倒的なリアリティーで描いた『世界侵略:ロサンゼルス決戦』、ウォンビンがハードなアクションで魅せる『アジョシ』など、えりすぐりの秋映画をお届け!

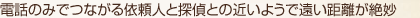


北海道出身の大泉洋が、ススキノを舞台に活躍する“探偵”を演じたスリリングなミステリー。バーにかかってきた1本の電話をきっかけに、小雪演じる謎の美女の思惑や1年前の殺人事件に“探偵”が巻き込まれていくストーリーは、複雑ながらもテンポよく描かれており、ラストに至るまで観客を飽きさせない。電話を通して依頼人と探偵の間に奇妙なきずなが生まれる一方で、相手のことは声しかわからないという一方的関係は、依頼人のために奔走する探偵が事件の裏にある個人的事情にまで踏み込めないことを暗示している。事件の当事者ではなく、結局は傍観者や狂言回しでしかありえない。考えようによってはこれ以上ないほど寂しい生き方だが、それだけに、松田龍平演じる相棒の高田とのユーモラスなやり取りは、仕事上のつながりにとどまらず、人と触れ合うことの温かみを感じさせる。そんな、シリアスでありながらコミカルな味わいも持つ“探偵”のキャラクターが強烈な本作。新時代の探偵物語として、ぜひシリーズ化してもらいたい作品だ。(編集部・福田麗)



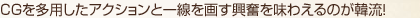


『母なる証明』では、マザコンで気弱な青年を演じていたウォンビンが、今度は寡黙な殺人キラーに大変身! 韓国でも大ヒットを記録した新作『アジョシ』は、謎の組織に連れ去られた女の子を、隣のおじさん(韓国語でアジョシ)が命懸けで助けにいくバイオレンス・アクション。そう、この作品、一見普通の男が実はとんでもなく強い殺人キラーだった! というリーアム・ニーソン主演の『96時間』の韓国版ともいえる設定だが、ハリウッドにも劣らぬ痛快アクション・エンターテインメント作に仕上がっている。『悪魔を見た』『オールド・ボーイ』のように、「そこまでやるか!」と思うほど、ねちねちと相手を懲らしめるバイオレンスシーンが定評の韓国映画界。その残酷さは本作でも健在だが、男たちがぶつかり合う韓国流の描写は、CGを多用して見せる現在のアクション映画と違う興奮を味わえる。2階から一気に飛び降りたり、銃やナイフを鮮やかに使いこなすウォンビンの体を張ったアクションもさることながら、徐々に韓国の裏社会が明かされていく演出も秀逸。女性の皆さんは、ウォンビンの鍛え上げられた肉体があらわになるシーン(韓流スターお約束!?)もお見逃しなく!(編集部・山本優実)



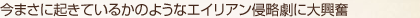
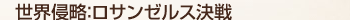

1942年にアメリカ軍がロサンゼルスに現れた未確認飛行物体を迎え撃った実話の後日談、という触れ込みだけに、エイリアンの侵略劇を、今まさに起きているかのような臨場感満載で描いたSFアクション。手持ちカメラを用いた撮影手法で徹底したリアリティーを追求していることから、「モキュメンタリー」と言っても過言ではないほど。エイリアンの脅威を、マンションに住む民間人の視点で映し出した『スカイライン-征服-』と同様、本作でも海兵隊員たちが手探りで敵の特徴や弱点を模索していくさまに緊張感が途切れない。銃撃戦をメインに、エイリアンと人類の攻防戦をとことんダイレクトに映している点も白眉(はくび)だ。仲間の兵士や民間人を束ねるアーロン・エッカートふんするベテラン軍曹は少々ヒロイック過ぎる感があるものの、銃を使えるかと尋ねる兵士に「この美ぼうを売りにしてきたんじゃないわ!」と返す、空軍女兵士役のミシェル・ロドリゲスは、男よりもマッチョな頼もしさ!(編集部・石井百合子)



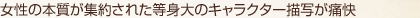


青年漫画誌「イブニング」に連載された女性漫画家・久保ミツロウの同名漫画を、テレビドラマ「アキハバラ@DEEP」「週刊真木よう子」の大根仁監督が映像化した本作。突然“モテキ”が訪れたさえない草食系男子が、4人の美女に翻弄(ほんろう)されながら成長していくというストーリーだが、「男目線の物語を描いているふりをしながら、女性目線で描いている」という久保と、そこに「男目線を加えた」という大根監督の共作で生み出されたキャラクター像は「『モテキ』を観れば、女がわかる」と言っても過言ではないほどリアル。女性は、女性キャラクターが過去の自分と重なれば、痛いところを突かれるかもしれないが、多彩なJ-POPの歌詞とシンクロしながら、人目をはばからず叫び、泣き、疾走する主人公の奮闘ぶりに、爽快(そうかい)感を覚えるはず。「森山未來がうらやましい」と映画館に足を運んだ男性には、赤裸々な女性キャラを通して女性の本質に気付いてもらいたいところだ。(編集部・島村幸恵)






昨年公開時に良作として静かなブームを巻き起こした『すべて彼女のために』が元ネタゆえ、どうしても比べられる運命にある本作。そんな下世話な心配もよそに、運命のはかなさや人間の弱さを『クラッシュ』『告発のとき』などで丁寧に紡いできた名匠ポール・ハギス監督が、サスペンスフルな中にも忘れたくない温かな人間愛をちりばめ、まったく別の作品を作り上げている。身に覚えのない殺人罪でとらわれの身となってしまった妻を必死に助け出そうとする夫で、大学教授というインテリ役を、クセのある役柄やアクションを得意とするラッセル・クロウが、意外なまでに熱を抑えた演技で魅了する。一方、オリジナル版でダイアン・クルーガーが演じた妻は、絶体絶命の状況下で悲壮感漂う姿が作品全体の印象を決定付けるほどの力を放っていたが、今回同役にふんしたエリザベス・バンクスは表情に乏しく、迫力を感じるまでに至らなかったのがちょっぴり残念。(編集部・小松芙未)










