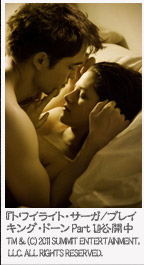エロスで語るヴァンパイア映画特集
型破りシネマ塾
型破りシネマ塾
エロスで語るヴァンパイア映画特集
アメリカでは『トワイライト』シリーズを頂点とする空前のヴァンパイア・ブームが続いている。一方で、このブームに満足していないヴァンパイア映画フリークも少なくないはず。そこでヴァンパイア映画には欠かせない「エロス」をキーワードに、当ジャンルに精通したライターがヴァンパイア映画の魅力をディープに解説。ヴァンパイア映画初心者から上級者まで、目からうろこ&納得のレア情報が満載です!(文 / なかざわひでゆき)
肉欲の罪を体現した初期ヴァンパイア映画
かつて映画界には「ヴァンプ女優」なる言葉が存在した。その第1号はサイレント時代に活躍した豊満な肉体派ハリウッド女優セダ・バラ。「妖艶(ようえん)な色香で男を誘惑して精気を吸い取ってしまうヴァンパイアのような女」というわけだ。このことが象徴するように、ヴァンパイアという存在にはエロスのにおいがつきまとう。人間の首筋から血を吸い取るヴァンパイア、抵抗しながらも恍惚(こうこつ)の表情を浮かべる犠牲者。その様子は性行為さながらともいえるだろう。十字架や聖水に弱いという定説からも想像がつくように、そもそもヴァンパイアとは根本的にアンチクライスト(反キリスト)な存在であるのだから、カトリック教会のいうところの「肉欲の罪」の体現者であっても何らおかしくない。いや、そうでなくてはならないのだ。そのように考えれば、エロスというものがヴァンパイア映画にとって最も重要なメタファーの一つであることが理解できよう。
映画史上で最初の重要なヴァンパイア映画といえば、サイレント期のドイツ映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922)。だが、ヴァンパイアの存在を世界的に認知させた最初の作品は、ユニバーサル・ホラーの金字塔『魔人ドラキュラ』(1931)だろう。そして、この作品でもエロスは重要なキーワードだった。もちろん、直接的な描写があるわけではないのだが、強烈な目力で美女をトリコにしてしまう異国なまりのダークな紳士ドラキュラ伯爵(ベラ・ルゴシ)そのものが、まさにフェロモンとセックスアピールの塊みたいなもの。さすがに今観ると、舞台のメソッドをそのまま映画に持ち込んだルゴシの演技は暑苦しすぎることこの上なしなのだが、当時の女性客はそれこそ映画の中のルーシーやミーナのように、邪悪で危険で官能的なドラキュラ伯爵の魅力に参ってしまったという。
さらに、ユニバーサルがその続編として制作した『女ドラキュラ』(1936)では、グロリア・ホールデンふんするドラキュラ伯爵の娘マリヤが登場。普通の女性としての人生を望む彼女が、己の吸血本能に逆らうことができずに若い美女たちを次々と餌食にしていく。そう、明らかにレズビアンとヴァンピリズムを重ね合わせ、人間を本能的に突き動かすエロスの強烈な力というものを、官能的でデカダン(=退廃的)なムードの中に描いているのだ。当時としてはかなり大胆な試みだったといえるだろう。


フリーセックスの時代とヴァンパイア
ユニバーサルからホラー映画の伝統を受け継いだイギリスのハマー・プロもまた、数多くのヴァンパイア映画を世に送り出した。クリストファー・リーがドラキュラを演じた『吸血鬼ドラキュラ』(1958)を筆頭に、『吸血鬼の接吻』(1963)や『凶人ドラキュラ』(1966)、『吸血鬼サーカス団』(1971)などなど。いずれもためらうことなくヴァンピリズムとエロスを濃密に絡めていたわけだが、中でもレズビアンをテーマにした「カルンシュタイン3部作」と呼ばれる『バンパイア・ラヴァーズ』(1971)と『恐怖の吸血美女』(1971)、『ドラキュラ血のしたたり』(1971)の3本は、当時のフリーセックス運動に呼応した映画界における性解放の気運を強く意識し、いずれもエロスを前面に押し出していた。特に、フランス映画『血とバラ』(1961)の原作でもあるジョゼフ・シェルダン・レ・ファニュの傑作怪奇小説「カーミラ」をベースにした『バンパイア・ラヴァーズ』は、従来のハマー作品らしい重厚なゴシック・ムードと大胆なレズビアン描写の組み合わせが功を奏した佳作だ。
また、1970年代にはスペインのカルト映画監督ジェス・フランコも、『ヴァンピロス・レスボス』(1970)や『吸血処女イレーナ・鮮血のエクスタシー』(1973)というソフト・ポルノ・タッチのヴァンパイア映画を残している。中でも異色なのは後者。いつでもどこでも半裸状態で発情し続けている女ヴァンパイア・イレーナなのだが、彼女が吸うのは血ではなくて体液。つまり、相手が男だろうと女だろうと構わず、オーラルセックスで精液やら愛液やらを吸い尽くして殺してしまうというのだ。そもそもいったいどこが処女やねん! 吸血ですらなかろうに! と突っ込みたくなる邦題はさておき、ヴァンピリズムとセックスをイコールにしてしまった大胆不敵さと率直さはユニークだ。ただし、ホラー映画としてはおろか、映画作品としても出来栄えはクズ同然なのだが。



ヴァンパイアとエロスと哀しみと
さらに、ベルギーの映画監督ハリー・クメールの日本未公開作『ドーターズ・オブ・ダークネス(英題) / Daughters of Darkness』(1971)も忘れてはなるまい。「血の伯爵夫人」として名高い実在の女吸血鬼エリザベス・バートリーが、若い新婚カップルを誘惑して手玉に取っていく。ここで重要なのは、ヴァンピリズムとエロスにフェミニズムを絡めている点であろう。400年以上も生きながらえるレズビアンのヴァンパイア・バートリー伯爵夫人は、支配者たる男からも時間からもモラルからも解放された自由の象徴だ。そんな彼女が旧態然とした女性の価値観に縛られる新妻ヴァレリーの官能のドアを開くことで、その女としての野性本能を覚醒(かくせい)させる。一方、偽りの愛を隠れみのにゲイとしての素顔をひた隠し、男らしさを盾にして妻をひざまずかせることでしか己の存在を正当化できない夫・ステファンは、たちまち自滅していく。アラン・レネの傑作『去年マリエンバートで』(1960)をお手本にした幻想的で耽美的な映像、そのヒロインだった名女優デルフィーヌ・セイリグが演じるバートリー伯爵夫人のディートリッヒのごときデカダンな色香なども素晴らしく、実にインテリジェントで官能的なヴァンパイア映画に仕上がっている。
そして最後にご紹介するのが、ヴァンパイアとエロスを語る上で絶対に外すことのできない人物。フランスの生んだ耽美ホラーの巨匠ジャン・ローランである。異形なるものの孤独と哀しみを耽美的なエロスの中に映し出し続けたローラン監督だが、中でも『The Rape Of The Vampire』(1967)や『催淫吸血鬼』(1970)といったヴァンパイア物は独壇場。幼いころに遭遇した女ヴァンパイアの面影を追い続ける青年を描いた『血に濡れた肉唇』(1975)などは、ロケ地となった古城廃虚の荒涼とした風景や全裸の女ヴァンパイアを演じるアニー・ベルのはかなげな美しさとも相まって、実に叙情的でもの哀しいヴァンパイア映画の傑作となっている。
近ごろのヴァンパイア映画は血のりやアクションばかりを優先し、肝心のエロスをなおざりにしたような作品が増えてしまった。もはやヴァンパイアである必要すらない『プリースト』(2011)や、低次元なお子様向け純愛ものに仕立てた『トワイライト』シリーズなんぞ言語道断。繰り返しになるが、アンチクライストたるヴァンパイアに「肉欲の罪」は必要不可欠なのだ。