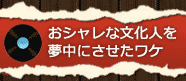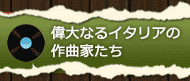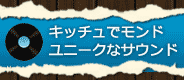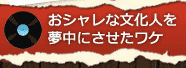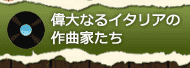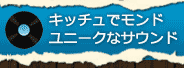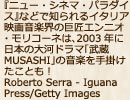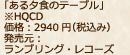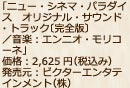サントラ特集第1弾:知るとハマるイタリア映画音楽の魅力
型破りシネマ塾
型破りシネマ塾
サントラ特集第1弾:渋谷系音楽フリーク必聴! 知るとハマるイタリア映画音楽の魅力
「映画を彩るサントラの魅力を語り始めたら止まらない」という映画ファンは多いに違いない。そんなサントラの中でも、興味深い歴史とポジションを確立しているイタリア映画の音楽の魅力をご紹介。イタリア映画音楽のルーツから日本や欧米の音楽シーンに与えた影響、おなじみのコンポーザーから筆者によるマニアックなおススメ作品まで、映画を観ていなくてもサントラだけで楽しむことができるイタリア映画音楽の魅力を解説します!
文/なかざわひでゆき
小西康陽ら渋谷系ミュージシャンを夢中にさせたイタリア映画音楽
かつて『黄金の七人』(1965)のサントラを彷彿とさせるフリッパーズ・ギターの名曲「恋とマシンガン」のヒット、そして小西康陽や橋本徹といったおシャレな文化人たちの後押しもあって、90年代渋谷系ブームの流れで人気を得たイタリア映画音楽。時代をさかのぼること1950年代半ば~60年代には『鉄道員』(1956)や『太陽はひとりぼっち』(1962)の主題歌が大ヒットし、現在でもAvanzレーベルのようにイタリア映画のサントラCD復刻を専門とするレコード会社が存在するくらい、日本における古いイタリア映画音楽の人気は根強い。しかも、この現象は日本に限ったことではないらしく、往年のイタリア映画音楽は欧米でも1990年代からクラブ・ミュージックでサンプリングされ、イギリスやフランスのクラブDJにネタとして使われ、ドイツやスペインでも専門のレコード会社が存在する。では、なぜそれほどまで古いイタリア映画音楽が人々を魅了し続けるのか? 熱狂的マニアを自認する筆者が、あくまでも独断と偏見で分析してみたい。
まず日本や欧米で人気の高いイタリア映画音楽というのは、主に1960~70年代の作品に集中している。この時代のイタリア映画音楽はメロディーが非常にポップでわかりやすく、おシャレで洗練されたアレンジが特徴的だ。それは当時のイタリア映画界に黄金期の勢いがあったこと、そしてクラシックやカンツォーネの伝統に根差したイタリア独特の音楽文化のおかげといえよう。実際、当時の作曲家はローマやミラノの音楽院で古典を学び、カンツォーネの作曲や編曲を経て映画界で活躍した人が圧倒的に多かった。巨匠エンニオ・モリコーネはその代表格だ。また、ピノ・ドナッジオやニコ・フィデンコのように、カンツォーネのシンガーソングライター出身という人も少なくない。さらに、第2次世界大戦後のイタリアでは米進駐軍によってもたらされたジャズが大変なブームとなり、1960年代にはイタリアン・モダン・ジャズの黄金期を迎えた。当然、映画音楽の世界でも多くの作曲家がその影響を受け、さらにロックやR&Bなどのアメリカ音楽を貪欲に吸収しつつ、イタリア人らしいエモーショナルでロマンチックなサウンドを作り上げていったのだ。
しかし、イタリア映画音楽が花開く上で最も重要だったのは、監督や製作者の音楽に対する考え方だといえるだろう。一般的に映画音楽というのはあくまでも“伴奏”であり、映画のストーリーを盛り上げる演出の一つに過ぎない。しかし、こと往年のイタリア映画において音楽は主演俳優並みに重要視され、下手をすると本編よりも音楽の方が有名になってしまうというケースも少なくなかった。ハリウッドでの仕事も多いモリコーネやドナッジオは「アメリカはイタリアと違って音楽に造詣の深い映画監督が少ない」という旨の発言をしているが、これはクラシックやオペラなどの伝統文化に根差した価値観からくるのだろう。それゆえに、イタリアでは映画音楽がそれ単体で成立してしまうほどの進化を遂げたのである。
モリコーネ、チプリアーニ……イタリアの偉大なる作曲家たち
そこで、次にイタリア映画初心者へおススメの作曲家およびその作品をご紹介しよう。まずは、やはりイタリア映画界が誇るマエストロ、エンニオ・モリコーネ。アクションからコメディー、ホラーに至るまであらゆるジャンルの映画を手掛けてきた彼は、その音楽スタイルも交響楽からジャズ、ロック、ラテン、ボサノバまで実に幅広い。その魅力は甘すぎない程度に抑えられた叙情的なメロディー・センスと、クールで実験性の高いアレンジにあると言えるだろう。もともと『荒野の用心棒』(1964)や『夕陽のガンマン』(1965)といったマカロニ・ウエスタンで注目された彼だが、その真骨頂とも呼べるのがセルジオ・レオーネ監督の壮大なる西部劇叙事詩『ウエスタン』(1968)。大西部に生きる誇り高きヒロインの決意と情熱を、勇壮かつ悲哀に満ちたメロディーで描いた『ジルのテーマ』は必聴だ。また、イタリアン・ボッサの傑作として名高い『ある夕食のテーブル』(1969・日本未公開)はスイートでおシャレなラウンジ・サウンドの宝庫だし、フレンチ・ポップスのごとき爽やかで切ないテーマ曲が意表を突く刑事アクション『非情の標的』(1972)、華麗なメロディーとグルービーなジャズ・ファンクを融合したフランス映画『パリ警視J』(1984)などもカッコいい。もちろん、ノスタルジックな『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)や『マレーナ』(2000)も、モリコーネならではの胸キュン・サウンドを堪能できるという意味でオススメだ。
一方、イタリア映画ならではの甘いメロディーを極めた作曲家がステルヴィオ・チプリアーニ。代表作『ベニスの愛』(1970)は、フランシス・レイの『ある愛の詩』(1970)とメロディーが酷似していることから裁判となり、結果的にレイがチプリアーニのメロディーに影響されたことを認めた。この人が奏でるスコアは、とにかく甘く切なく美しい。しかも、恋愛映画のみならずアクションやサスペンス、ホラーでも、その大いなるロマンチストぶりを遺憾なく発揮してしまう。日伊合作『ラストコンサート』(1976)は音楽だけで観客の涙を誘うに十分だったし、B級パニック・ホラー『テンタクルズ』(1977)や『ナイトメア・シティ』(1980)は音楽の完成度が本編を上回ってしまった好例だ。
また、『イル・ポスティーノ』(1994)でアカデミー賞を獲得したルイス・エンリケス・バカロフも美しいメロディーに定評のある作曲家。中でも、タランティーノ監督『キル・ビル』(2003)のアニメ・シーンで使用された『怒りのガンマン/銀山の大虐殺』(1969)のテーマ曲は鳥肌モノの傑作だ。シチリア風の哀愁に満ちた旋律と軽快なサンバのリズムがマッチした『悪い奴ほど手が白い』(1967)も素晴らしい。
女性のため息を使用!? 実験的でユニークなサウンドにも中毒作用あり
そして、イタリア映画音楽といえば、キッチュでモンドでグルービーな楽曲の宝庫としても人気が高い。その代表格がピエロ・ウミリアーニの「マナ・マナ」だ。もともとは『フリーセックス地帯を行く/天国か地獄か』(1968)というエロ・ドキュメンタリー映画の挿入曲だったが、アメリカの「セサミストリート」で使用されたことをきっかけに世界中で人気を博し、日本でもよくテレビのジングルに使われている。ウミリアーニはモダン・ジャズ畑でも有名な作曲家で、彼の手掛けた映画音楽は斬新かつユーモラスな実験性に富んでおり、どれもハズレがない。
また、アルマンド・トロヴァヨーリの手掛けた『セッソ・マット』(1973)のテーマ曲も、カバー・バージョンやリミックスが存在するほど有名だ。女性のため息やスキャットをコラージュしたファンキーなサウンドは、一度聞いたら耳にこびりついて離れない。トロヴァヨーリもまたジャズに精通した人物で、シャバダバ・シャバダバのスキャットでおなじみの『黄金の七人』(1965)も彼の作品。その一方、『特別な一日』(1977)や『マカロニ』(1985)ではイタリア人らしい叙情的メロディーにも才能を発揮しており、知れば知るほど奥の深い作曲家だ。
他にも、『刑事』(1959)や『ブーベの恋人』(1963)のカルロ・ルスティケリ、『世界残酷物語』(1962)のリズ・オルトラーニ、『華麗なる殺人』(1965)や『南海のフリーセックス』(1968)のピエロ・ピッチォーニなどなど、往年のイタリア映画界には素晴らしい作曲家が数え切れないほどいた。リアルタイムではレコード化されなかった作品も、今やCDで続々と手に入るようになった。一度ハマったらやめられない止まらない、それがイタリア映画音楽の醍醐味(だいごみ)だといえよう。