第55回『キャプテン・フィリップス』『恋するリベラーチェ』『清須会議』『ウォールフラワー』『もらとりあむタマ子』
今月の5つ星

前田敦子がぐうたら女子にふんする『もらとりあむタマ子』、笑いの匠・三谷幸喜監督が、柴田勝家や羽柴秀吉らが一堂に会した歴史的行事を題材にしたコメディー『清須会議』、マイケル・ダグラスが「世界が恋したピアニスト」にふんした『恋するリベラーチェ』など、万人に響く娯楽大作からツウ好みの異色作まで、バラエティー豊かなラインナップがズラリ!


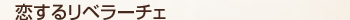

悪趣味ともとれるド派手な衣装と絢爛(けんらん)豪華なステージで、希代のエンターテイナーとして活躍したピアニスト、リベラーチェの私生活を追った恋愛ドラマ。同性愛者であることを最後まで隠し続けた彼が、年齢も立場もかけ離れた一人の男性と出会い、死を迎えるまでを描く。これまでのイメージを一新する、ド派手なケバケバしい衣装に身を包んだマイケル・ダグラスの姿は、一目で吹き出すこと必至。下手をすればただ悪趣味で独占欲が強い人物と映りかねないリベラーチェを、常に大衆を喜ばせることを考え、愛にあふれた人物として好演しており、その人間味あふれる魅力から最後まで目が離せない。また、そのリベラーチェがマット・デイモン演じる恋人スコットを、自分そっくりに整形させる危うい関係を、はかない愛情の物語として描き出す スティーヴン・ソダーバーグ監督の演出にも舌を巻くばかり。「世界が恋したピアニスト」の異名の通り、鑑賞後にはリベラーチェのことを愛さずにはいられない一本となっている。(編集部・入倉功一)






三谷幸喜監督が17年ぶりに書き下ろした小説を自ら映画化した痛快群像劇。本能寺の変で織田信長が亡くなった後、柴田勝家や羽柴秀吉らが一堂に会して、一滴の血も流すことなく、織田家後継者と領地配分が決まった清須会議の全容を笑いとスリリングな駆け引きを交えて描く。正月のオールスタードラマも真っ青の超豪華キャストが、三谷演出のもと、これまで演じたことのないようなキャラクターを、喜々として演じている姿が印象的。これまでの三谷作品に見られるようなギャグの連発はないものの、思わず吹き出してしまうようなヒネリのきいたセリフや、独特の間合いが随所にちりばめられており、三谷ファンにはたまらない仕上がりとなっている。大泉洋が、「人たらし」であったという人物像そのままに、魅力たっぷりに演じた羽柴秀吉と、役所広司が絶妙なオトボケ演技を発揮した柴田勝家が繰り広げる、恋のバトルも爆笑必至! 鈴木京香や剛力彩芽がお歯黒姿で登場したり、イケメン妻夫木聡や、伊勢谷友介が付け鼻で織田家の男を演じていたり、キャストたちの意外な変身ぶりも大いに楽しめるはずだ。(編集部・森田真帆)



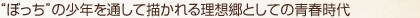


“ぼっち”だけれど、音楽と本が好きで、それをきっかけに破天荒な兄妹と友達になる。みんなにはバカにされているけど、作家だったという国語教師にだけは認められる。そして、彼らに導かれるままに大人になっていく……本作で描かれるそれらは、まさしく理想郷として作り上げられた青春時代だ。舞台が1991年、原作の出版が1999年、映画化が2012年だから、それぞれには約10年のタイムラグがあるが、そのいずれの時代に青春を過ごした人にも通じる作品になっているのは、本作が理想化されているがゆえに普遍的な、青春の影ともいうべき作品だからだろう。成長に伴う痛みさえも、青春を彩るものとしてここでは昇華されているのだ。賛否両論はあれども、そのことでより広範な作品になったことは間違いない。ローガン・ラーマン、エマ・ワトソンといった若い俳優陣も素晴らしいが、特にエズラ・ミラー。作中では最も大人びた役柄を演じていた彼が実年齢では上記3名の中で最も若いのは驚きだ。新たな才能に立ち会えるのも、青春映画の醍醐味(だいごみ)だろう。(編集部・福田麗)
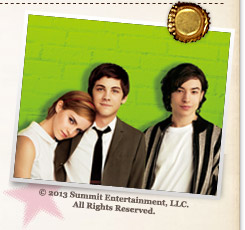





『苦役列車』で女優としての新境地を開拓した元AKB48の前田敦子と、その才能を引き出した山下敦弘監督が再びタッグを組んだ本作。何といっても見どころは、大学卒業後、父親が一人暮らす実家に戻ってひたすら食っちゃ寝のぐうたら生活を送る主人公・タマ子を演じる前田の演技。自分は働きもしないくせに「これだから今の日本はダメなんだ」と平然と言ってのけ、「就職活動くらいしろ」という父親の言葉にも「いつか働く。少なくとも今ではない」と意味のわからない理屈で逆ギレするダメダメ女子を、どこか吹っ切れた表情で演じる前田がとにかく愛らしい。普段からちょっぴり気だるそうな雰囲気をまとう彼女にはこれ以上ないくらいピッタリな役で、「あれ? 前田敦子って意外と演技うまい?」なんて思う人も多いだろう。地味ではあるが、心地よいクスクス笑いの止まらないすてきな作品だ。(編集部・中山雄一朗)



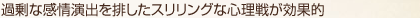
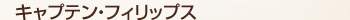

2009年のソマリア海域人質事件をテーマに、海賊に拉致されたコンテナ船のフィリップス船長(トム・ハンクス)の緊迫した4日間を描いた『キャプテン・フィリップス』。トム・ハンクス=「感動作」というイメージが強いが、本作には良い意味で裏切られる。というのも、感動の実話にありがちな「泣かせ」を全面に出さず、主人公の苦境を必要以上にアピールせず、海賊と船長の行動を対比的に見せることで、重厚かつスリリングなサスペンスに仕上がっていたからだ。拉致された船長が乗る救命ボートで繰り広げられる心理戦。押し寄せる波に酔い、換気も十分にできる状態ではない狭いボートの中で、次第に精神的に追い詰められていく両者。目を見張るような命懸けの駆け引きや、目をギョロギョロさせて銃を片手に興奮する海賊の様子など、極限状態を見事に表現。船長が救出されるという事実を知っていても、ハラハラさせられる。また、船長奪還を試みるアメリカ海軍の行動にも、より緊迫感をあおられる。ここまでまとめられるのは、まさにポール・グリーングラス監督のセンス。そして、こうした悲惨な状況にひるむことなく奮闘した船長が、ぷつんと糸が切れたように感情を爆発させるラストシーンには注目だ。ハンクスは3度目のオスカー受賞もあり得るかも!?(編集部:山本優実)










