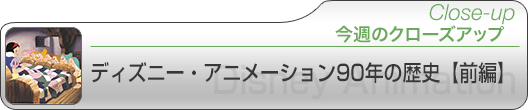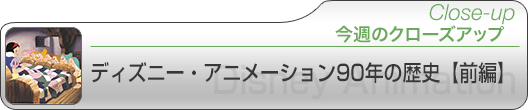『白雪姫』で大きな成功を収めたディズニーだったが、以降はヒット作に恵まれず、第2次世界大戦末期には深刻な経営危機を迎えていた。その危機を救うため、『バンビ』以来8年ぶりの長編アニメーションとして製作されたのが、シャルル・ペローの童話を原作にした『シンデレラ』だ。1944年に製作がスタートし、1950年の完成までに総勢750名のスタッフが投入されたと聞いただけでも、破格の製作規模だったことがわかるだろう。それは製作費にも表れており、『白雪姫』の約2倍となる290万ドル(2億9,000万円)が費やされた。結果的に『シンデレラ』は8,500万ドル(85億円)というディズニー最高の興行収入(当時)を記録し、ディズニーの完全復活、そして黄金期の到来を告げることとなる。(1ドル100円計算。以下同)
|
|
 |
『シンデレラ』より
RKO Radio Pictures / Photofest / Zeta Image |
|
|
『シンデレラ』が発表された1950年には、もう一つ、ディズニーのアニメーションを語る上で欠かせない出来事がある。ベテランアニメーターたちを指した「ナイン・オールド・メン(9人の古株)」という呼称が誕生したのだ。「ナイン・オールド・メン」の前身となったのは1940年に設立されたアニメーション部の管理を補佐するアニメーション幹部会で、当時は議題ごとにメンバーが変更されていたが、1950年に9人のスーパーバイジング・アニメーターで固定された。彼らの通称となっている「ナイン・オールド・メン」はもともと、最高裁判所の9人の判事を指す言葉だったが、ウォルトがその呼称を気に入ったため、彼らを呼ぶ言葉として使われるようになった。「ナイン・オールド・メン」のメンバーは以下の通り。
・レス・クラーク(1927年入社)
・ウォルフガング・ライザーマン(1933年入社)
・エリック・ラーソン(1933年入社)
・ウォード・キンボール(1934年入社)
・ミルト・カール(1934年入社)
・フランク・トーマス(1934年入社)
・オリー・ジョンストン(1935年入社)
・ジョン・ラウンズベリー(1935年入社)
・マーク・デイビス(1935年入社)
入社年を見ればわかるように、彼らは『白雪姫』以前からディズニーに参加しており、その栄光の時代を共に作ってきた。前項で紹介した作品には全て、彼らのうち何人かが関わっている。(彼らが9人そろって参加したのは『シンデレラ』『ピーター・パン』など、わずかな作品しかない)
|
|
 |
「ナイン・オールド・メン」のオリー・ジョンストンとフランク・トーマス
Vince Bucci / Getty Images |
|
|
ここでは彼らの業績を個々に取り上げることはしないが、ディズニー・アニメーションの名キャラクター・名シーンのほとんどは彼らのうちの誰かが担当したといって差し支えないだろう。そしてまた、彼らはアニメーションの制作過程も大きく変えた。これまでのディズニーの長編作品では、1人のアニメーターが1人のキャラクターを担当することになっていた。だが、彼らはそれを、1人のアニメーターが担当カットのキャラクター全てを受け持つようにした。これにより、一つのシーンにおけるキャラクター同士の掛け合いの妙が生まれることになったのだ。
|
|
 |
「ナイン・オールド・メン」が全員参加した『ピーター・パン』
RKO Radio Pictures Inc./Photofest |
|
|
『シンデレラ』の後も、ディズニーは『ふしぎの国のアリス』(1951年)、『ピーター・パン』(1953年)、『眠れる森の美女』(1959年)といった今なお語られることの多い名作を連発。また、リアルタイムで作品が紹介されていなかった日本でも1950年代からは旧作・新作が続々と公開され、手塚治虫をはじめとする著名人にも多くのファンが生まれた。
だが、創業以来常に製作の指揮を執っていたウォルト・ディズニーが1966年末に死去すると、雲行きは途端に怪しくなる。ウォルトと共にスタジオを支えてきた「ナイン・オールド・メン」のメンバーには映画製作の第一線から退いた者もおり、一つの時代が終わりに向かいつつあったのだ。そんな中で一人気を吐いていたのが、「ナイン・オールド・メン」のウォルフガング・ライザーマンで、彼はウォルトの死後第1作となった1970年の『おしゃれキャット』から1981年の『きつねと猟犬』まで、プロデューサーとして製作の指揮を執り、スタジオを支えていた。 |
|
 |
大のディズニーファンで知られた手塚治虫
Sankei Archive/ Getty Images |
|
|
それでも、スタジオの斜陽は確実に訪れており、ウォルフガングも1980年に引退。そのころには他の「ナイン・オールド・メン」のメンバーも退社しており、1980年代のディズニーは「暗黒時代」とも呼ばれる低迷期に入ってしまう。実際、このころの作品には批評的にはもちろん、興行的な失敗作も数多い。これが持ち直すのは、ディズニーの第2期黄金期の立役者であるマイケル・アイズナーのCEO就任、そしてアイズナーが連れてきたジェフリー・カッツェンバーグが映画部門の責任者に就任した1984年以降のことだ。
|
|
|
|
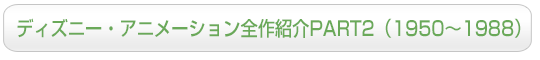 |
○『シンデレラ』(1950年)
言わずと知れたディズニーの代表作。シャルル・ペローの童話を原作に、独自の解釈を盛り込んだミュージカル作品に仕立てている。「ナイン・オールド・メン」全員がアニメーション監督として参加しており、まさにディズニーの粋ともいえる技術が注ぎ込まれた作品になっている。また、「シンデレラ」の実写モデルとしては、女優のヘレン・スタンリーが起用されている。彼女は「シンデレラ」だけでなく、『眠れる森の美女』のオーロラ姫、『101匹わんちゃん』のアニータ・ラドクリフのモデルにもなっており、まさに生きたディズニープリンセスといえる存在になった。
|
|
|
|
○『ふしぎの国のアリス』(1951年)
原作は、ウォルト・ディズニーが映画化を熱望していたというルイス・キャロルの童話。1933年にウォルトは原作を読んでほれ込み、その5年後の1938年には映画化権を取得していた。だが映画化は困難を極め、その理由としては原作に主だったストーリーがないこと、またヒロイン・アリスのキャラクターが弱かったことなどが挙げられている。興行的にはそれほど振るわなかったものの、「ハートの女王」や「チェシャ猫」「トゥイードルディーとトゥイードルダム」といったキャラクターのイメージを決定付けた功績は大きい。
|
|
|
|
○『ピーター・パン』(1953年)
原作はジェームズ・M・バリーの戯曲。『ふしぎの国のアリス』に続き、こちらも戦前からウォルト・ディズニーが映画化を企画していた。アニメーションの技法としては、まず実写用の俳優を使って撮影し、それを基にアニメーションを制作するという手法が採られている。これは『シンデレラ』でも採用されていたが、『ピーター・パン』での演出ははるかにこなれており、その躍動感は観る者をわくわくさせてくれる。フック船長のキャラクターは、その典型だろう。また、この作品は「ナイン・オールド・メン」全員が参加した最後の長編映画としても知られている。
|
|
|
|
○『わんわん物語』(1955年)
純粋な長編アニメーション映画としては、ディズニー初の完全オリジナルストーリー。1930年代後半から練っていた企画がようやくまとまったもので、そう考えると、このころのディズニー・アニメーションは戦前から企画されていたものが非常に多い。アニメーションとしては初のシネマスコープ作品として制作され、そのために製作費は当初の予定をはるかに上回った。だが、興行的には成功を収めている。
|
|
|
|
○『眠れる森の美女』(1959年)
生前のウォルト・ディズニーが関わった最後の童話原作の作品。この作品にはウォルトも力を入れており、製作に取り掛かったのは1951年。当初は1955年に公開を予定していたが、2度の延期を経て、1959年にようやく完成した。スタイリストのエイヴィンド・アールのインスピレーション・スケッチを基に背景が描かれ、キャラクターは背景に合わせてデザインが変更されるという、「キャラクターありき」ではなく「美術」「世界観」ありきで制作された作品だけあって、これまでのディズニー作品とは一線を画した美術は実に見応えがある。ただし、興行的には振るわなかった。全てが手作業で行われた最後の長編でもある。
|
|
|
|
○『101匹わんちゃん』(1961年)
ドディ・スミスの小説を原作に、ダルメシアンたちの冒険を描いたファミリーアドベンチャー。1996年には実写版リメイクの『101』が公開されたことも記憶に新しいディズニーの「動物もの」の代表作。この作品からセルに転写する作業にはトレスマシンが導入され、作業効率が飛躍的に向上した。その証しが、タイトルにもなっている101匹のわんちゃん(ダルメシアン)の描き込みだろう。これだけ多くの犬を一気に登場させることができたのは、トレスマシンの存在が大きい。
|
|
|
|
○『王さまの剣』(1963年)
原作はアーサー王伝説を基にしたT・H・ホワイトの小説。日本での知名度はいまいちながらも、そのクオリティーを含め、語るべきところは多い。ディズニー・アニメーションの長編映画で「ナイン・オールド・メン」が初めて単独監督(ウォルフガング・ライザーマン)を務めた作品であるということ、後に『メリー・ポピンズ』などを手掛ける作曲家のシャーマン兄弟が初めて音楽を手掛けたディズニー・アニメーションであるということ、そして生前のウォルト・ディズニーが公開を見届けた最後の作品であるということだ。
|
|
|
|
○『ジャングル・ブック』(1967年)
原作はノーベル賞作家ラドヤード・キプリングの小説。公開を見届けることはできなかったものの、ウォルト・ディズニーの遺作となった。監督は前作に引き続き、ウォルフガング・ライザーマンが単独で務めた。以降、ウォルフガングは『ビアンカの大冒険』までの長編アニメーション映画の全作で製作・監督を務めることになる。彼がよく使った手法としては、自身の過去の絵を再利用することが知られている。例えば、本作のオオカミの子どもは『101わんちゃん』の犬のスケッチが基になっている。
|
|
|
|
○『おしゃれキャット』(1970年)
ウォルト・ディズニーの死後第1作。4年という製作期間が取られ、「ナイン・オールド・メン」のうち4人が参加した。この作品に関わったアニメーターにはベテランがそろっていたというから、いかにディズニー社がこの作品を重要視していたかがよくわかる。結果的に興行的な成功を収めたことで、スタジオは安堵のため息をついたという。人気キャラクター、子猫の「マリー」の登場作品でもある。
|
|
|
|
○『ロビン・フッド』(1973年)
中世イングランドの伝説「ロビン・フッド」の登場人物を動物に置き換えたファミリーアニメーション。企画自体はウォルト・ディズニーの存命中からあったものを、ウォルフガング・ライザーマンが監督を務めて完成にこぎ着けた。ただし、予算は前作『おしゃれキャット』の半分以下に削られるなど、当時のスタジオの厳しい内情がうかがえる。そのためか、ダンスシーンには『白雪姫』『ジャングル・ブック』『おしゃれキャット』で使われたシークエンスが再利用されている。
|
|
|
|
○『クマのプーさん』(1977年)
ディズニーが誇る人気キャラクター「プーさん」初の映画作品。ただし、作品自体は過去に発表された中編映画を組み合わせたもので、残念ながら長編アニメーションとして改めて語るべきことはほとんどない。「プーさん」のオリジナル劇場アニメーションは2011年の『くまのプーさん』まで待つ必要がある。
|
|
|
|
○『ビアンカの大冒険』(1977年)
原作はマージェリー・シャープの小説。この作品の制作中に「ナイン・オールド・メン」の一人であるジョニー・ラウンズベリーが死去し、同作をもってミルト・カールは引退。残っていた他のメンバーも公開直後にほとんどがディズニーを去った。その意味では、ディズニーの世代交代の境目となった作品といえる。作品自体はヒットし、1990年には続編の『ビアンカの大冒険/ゴールデン・イーグルを救え!』も製作された。ただし前述の通り、当時のメインスタッフは入れ替わっているため、中身は別物になっている。
|
|
|
|
○『きつねと猟犬』(1981年)
原作はダニエル・P・マニックスの小説。24本目のディズニー長編アニメーション映画にして、「ナイン・オールド・メン」が関わった最後の作品。代わりに若い世代が台頭しており、ジョン・ラセター、ジョン・マスカー、ロン・クレメンツ、ブラッド・バード、ティム・バートン、ヘンリー・セリックといった後のディズニー……というよりも、現在のアニメーション界を支える面々がスタッフとして参加している。ちなみに彼らは「ナイン・オールド・メン」のエリック・ラーソンが立ち上げたトレーニングプログラムの出身者であり、脈々とディズニーの伝統が受け継がれているさまがうかがえる。
|
|
|
|
○『コルドロン』(1985年)
原作はロイド・アレクサンダーの「タランと角の王」。興行的な大失敗作になり、ディズニー暗黒期の象徴ともいえる作品になってしまった。ただし作品に見るべきところがないかというとそんなことはなく、『きつねと猟犬』同様、今や大物となった当時若手のアニメーターが参加していることに加え、タイトルにもなっているコルドロンにコンピューターによる作画が用いられるなど、後の作品につながる要素が多々ある。また、ディズニーのアニメーション映画で初めてPG指定を受けたことでも知られている。
|
|
|
|
○『オリビアちゃんの大冒険』(1986年)
イヴ・タイタスの児童書「ねずみの国のシャーロック・ホームズ」シリーズを原案にしている。後に『リトル・マーメイド/人魚姫』『アラジン』といったディズニーのニュークラシックを手掛けることになるロン・クレメンツとジョン・マスカーの初の共同監督作品。製作費・製作期間とも恵まれない状況の中での発表になったが、娯楽作品として高い評価を得た。ただし、“ニュークラシック”とはかなり趣が異なるので、期待しすぎると肩透かしを食らうかもしれない。
|
|
|
|
○『オリバー/ニューヨーク子猫ものがたり』(1988年)
チャールズ・ディケンズの長編小説「オリバー・ツイスト」を大胆に翻案したミュージカル映画。1984年にディズニーの映画部門の責任者に就任したジェフリー・カッツェンバーグが持ち込んだ企画が基になっており、新生ディズニーの始まりともいえる作品になっている。『コルドロン』『オリビアちゃんの大冒険』でも用いられていたコンピュータによる作画を多用しており、ディズニーの長編アニメーションでは初めてコンピューター・アニメーションによる部署が設立された。興行成績は持ち直し、この作品で用いられたミュージカルスタイルは後のニュークラシックの作品群に大いに影響を与えることになる。
|
|
|
|

【関連リンク】
『アナと雪の女王』劇場公開 記念キャンペーンページ
【参考文献・資料】
「ディズニーアニメーション 生命を吹き込む魔法 - The Illusion of Life -」フランク・トーマス、オーリー・ジョンストン 翻訳:スタジオジブリ 日本語版監修:高畑勲、大塚康生、邦子・大久保・トーマス 徳間書店(2002年)
「創造の狂気 ウォルト・ディズニー」ニール・ゲイブラー 翻訳:中谷和男 ダイヤモンド社(2007年)
「DISNEY THE FIRST 100 YEARS - ディズニークロニクル1901-2001」デイヴ・スミス、スティーヴン・クラーク 翻訳:唐沢則幸 講談社(2001年)
「Disney A to Z/The Official Encyclopedia オフィシャル百科事典」デイヴ・スミス ぴあ(2008)
「ディズニーの芸術 - The Art of Walt Disney -」クリストファー・フィンチ 翻訳:前田三恵子 講談社(2001年)
(C)2014 Disney
|
| |
文・構成:編集部 福田麗 |