『グラスホッパー』生田斗真×浅野忠信×山田涼介インタビュー
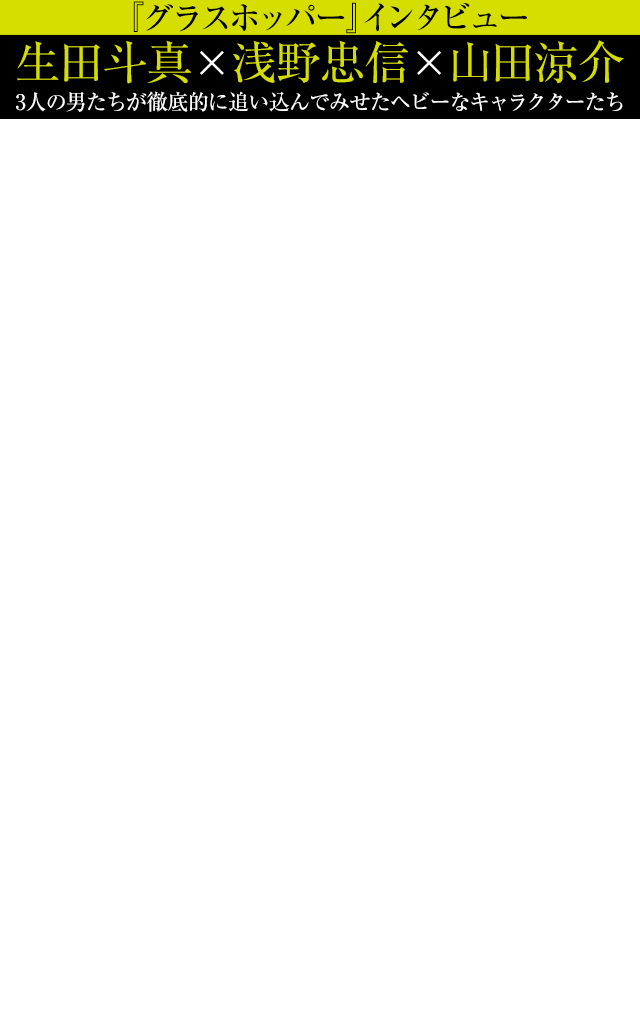
140万部突破の伊坂幸太郎のロングセラー小説「グラスホッパー」がついに映画化された。3人の男の視点で展開する伊坂ワールドを体現するのは、生田斗真、浅野忠信、山田涼介。困難な役どころに挑んだ「戦友」たちが、演じたキャラクターと自分自身の関係を語った。

Q:伊坂幸太郎さんの作品の中でも特に人気の高い小説の映画化ですね。
生田斗真(以下、生田):数ある伊坂作品の中でも、伊坂さん自身がすごく大切にされている原作を映画化できるということに、まず驚きました。伊坂さんが『脳男』をご覧になったそうで、「瀧本(智行)監督なら『グラスホッパー』の映画化を、ぜひお願いします」ということで実現したんです。その瀧本さんが「生田がやるならやりましょう」と。それで重圧が二重に乗っかってきました(笑)。怖さはありましたが、すごく信頼している監督ですし、信頼できる原作なので、思い切って飛び込みました。お客さんと一緒に驚いて、お客さんを物語の中に巻き込んでいく。鈴木というキャラクターはとっても魅力的だったし、自分にとっても新しい挑戦になると思って頑張りました。
浅野忠信(以下、浅野):これまで殺し屋を何度か演じているんですけど(2001年の『殺し屋1』など)これは今までにない殺し屋で面白いなと思いました。台本を読んだ後に原作を読んだんですけど、実は小説を読むのが苦手で。台本ばかり読んでいたので、最初は「小説、読めるかな?」と思っていました。でも、あのハンコが来るワクワク感! あれで読めてしまうんです。すごく引き込まれてしまう小説でしたね。
山田涼介(以下、山田):伊坂さんワールドが炸裂していると思いましたし、人間それぞれの微妙なズレを描くのが絶妙だなと思いました。人それぞれが抱えている悩みや、その一つの悩みから広がっていくパラレルワールドが面白かったです。蝉という殺し屋役は、正直できないんじゃないかと思いました。今でも自信はないですけど、全力を出したので、あとは観てくださった方に判断していただけたらと思います。
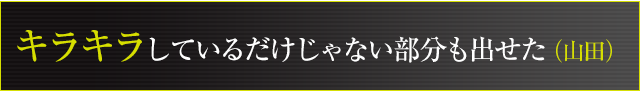
Q:復讐のために闇世界に飛び込む鈴木。極めて対照的な鯨と蝉という殺し屋二人。映画『グラスホッパー』はキャラクターの錯綜(さくそう)劇が絶妙な効果をあげています。皆さんはご自身の役を、どのように映画に反映させようと思われましたか。
生田:僕は監督から「弱さを強めに出してほしい」と言われていたので、ちょっとしたことで悲鳴をあげるとか、走り方が汚いとか、自分なりのスパイスはちょこちょこ入れました。「余計なことをしない」というのもテーマでした。変な走り方もやり過ぎるとよくないので、いかに自然に見せるか、その瀬戸際で戦っていたような気がします。あと、メガネをいつも曇らせていたんです。鈴木はレンズをさわっちゃうから、いつも曇っているという設定を考えて。メガネを曇らせると靄がかかるので、夢を見ているような状態というか、現実味のない視界になっていましたね。自分にとっていいアイテムだったと思います。
浅野:この撮影に入る前、俳優としていろいろな葛藤がすごくあった時期だったんです。それに対して、(気持ちの)決着がつけられていませんでした。そんな中、この特殊な殺し屋役をいただいて。鯨は悶々としている男ですし、亡霊に悩まされている男ですから、自分の役者としてダメな部分とか、一方でダメであっていいんじゃないかと思える部分を、現場で出していたと思います。役者としての今日までと鯨が持つ何かを、うまいことこじつけてやっていた気がしますね。僕は「何で?」と思うことに対して目を閉じるのが苦手なので、つい考えてしまう。でも鯨はそんなことは考えない。手放せばいいんだと。しんどかったけど、いいチャレンジでした。
山田:初日にいきなり大量に人を殺すシーンを課せられたので、いきなり壁にぶち当たったんですけど、やってみたらその壁を壊すのは簡単で、面白さが感じられました。蝉の内なる部分を隠しながら、最後の最後に出していく。その過程を頭の中でちゃんと整理しながら徐々に蝉になれていたのかなと思います。アクションに関してはダンスを普段やっているので、動けるだろうなと思っていたんですが、まったく別物でした。見えないところでもちょっとした技をかけたり、そういう作業がすごく難しかったです。
生田:でも体にキレがあったし、あと目が鋭かった。普段、Hey! Say! JUMPというグループで歌ったり、いろいろなことをやっている中で、「もっとぶっ飛んだこともやりたいんだよ!」という思いもどこかにあって、その思いがこの蝉というキャラクターに全部注入されていた感じがする。観ていて気持ちよかったよ。
山田:キラキラしているだけじゃない部分も出せたかなと思っています(笑)。
Q:アクションといえば、クライマックスの鯨と蝉の決闘シーンは、迫力がありましたね。
山田:本当に鯨を殺すぐらいの気持ちで、シーンに入っていったんです。
浅野:いやあ、怖かったよ(笑)。
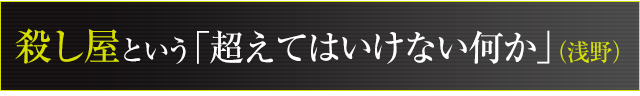
Q:蝉にはブレがないですよね。小説ならではの、そして映画にとてもフィットするキャラクターだと思います。
山田:蝉の夢は鯨を殺すこと。蝉にとっては「僕の夢は野球をすること」ぐらいの感覚なんです。それってすごく不思議だし、今までにない感覚でした。だけどどこか共感できる。人間って、一歩間違ったらこうなるんだろうなっていう怖さもちょっとありました。蝉の気持ちに寄り添えない自分もいましたが、普段自分が感じないことを感じるからこそ、どんどん「蝉色」に染まっていけたんです。
Q:この映画を観て、あらためて「殺し屋」や「復讐」というものは、映画と相性がいいなと感じました。
浅野:僕が最初に殺し屋を演じたのが「FRIED DRAGON FISH THOMAS EARWING'S AROWANA」(1996年の岩井俊二監督によるドラマ)だったと思うんですけど、あのとき台本を読んで、役にとんでもない魅力を感じていたんです。それはたぶん、自分が普段行けないところに、その人物は行っていると思ったからだと思います。殺しって絶対やってはいけないことだし、絶対あり得ないようなことが、一番わかりやすく出るのが殺し屋という役どころなのかもしれない。ホントはそこにヒーロー像を求めてはいけないんだけど、映画になると「何とも言えないもの」があって、「乗り越えてはいけない何か」に一番近い存在というか。これは映画にはもってこいのキャラクターですよね。
生田:復讐ってラブストーリーとは違って、一般的に経験したことがないものなんですよね。恋なら共感しやすいけど。「復讐したい」と思うことって、そんなにないじゃないですか。それだけに、復讐する側を演じるのはなかなかヘビーでしたし、その状態をずっと保っていないといけないっていうのは、結構過酷でした。でも、なぜなんでしょうね。復讐を描く映画が世の中に求められるのは。そこにはフィクションとして観たい何かがあるんでしょうか。そういう意味では『グラスホッパー』というのは、復讐劇だし、殺し屋の話なんだけど、きちんと共感できる。気持ちよく映画館から出られる作りになっていると思います。

鯨と蝉が決闘するクライマックス。「殺すつもりでいきました」と語る山田と、「怖かったよ」と笑う浅野。「監督に『こんな主役っぽくない主役はいないでしょう?』と言われた」と楽しそうに振り返る生田。こんなに殺気立った山田を、こんなに受け身な浅野を、そしてこんなに右往左往する生田を、見たことがなかった。新生面を開拓するために、それぞれが自身を徹底的に追い込んだからこそ得られた何かがあるのだろう。3人の男たちの語らいは、充実感に満ちていた。(取材・文:相田冬二)
映画『グラスホッパー』は11月7日より新宿ピカデリーほか全国公開


