岡田准一&妻夫木聡、恐怖映画スパルタの現場を振り返る
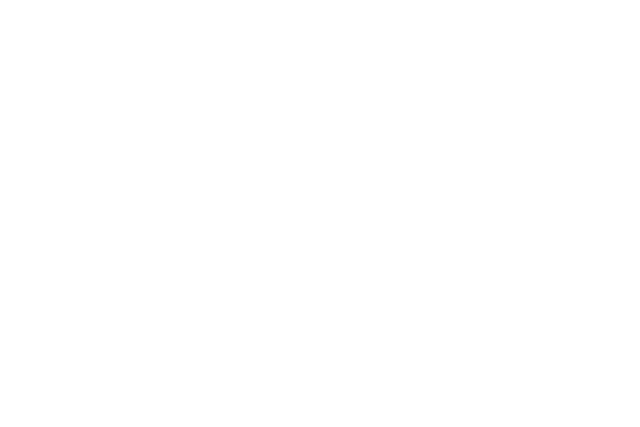
『告白』の鬼才・中島哲也監督が、澤村伊智の第22回日本ホラー小説大賞受賞作「ぼぎわんが、来る」を映画化した『来る』。「何か」にとり憑かれたある家族に起きる怪現象と、それを祓おうとする者たちを描くホラー小説を原作としながらも、「描きたいのは『人間』の面白さ」と中島監督が語る通り、人間の心の闇の恐ろしさを描いた作品となっている。本作で、「何か」に翻弄される主人公のオカルトライター・野崎をワイルドな風貌で演じた岡田准一と、妻子にも脅威が及ぶ怪現象を野崎に相談するイクメンパパ・田原を演じた妻夫木聡が、そのこだわりの強さから過酷とも噂される中島監督の撮影現場を振り返った。(天本伸一郎)
最も恐ろしいのは人間
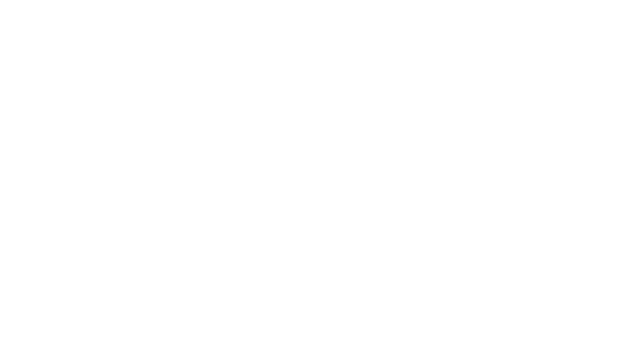
Q:岡田さんはホラーが苦手で、台本も怖くてなかなか読み進められなかったそうですね。
岡田准一(以下、岡田):中島監督から出演依頼のお手紙をいただき、人間の怖さの中にホラーを足したような作品をやりたいということでした。台本を読んでみて、完成度が高くて面白いと感じたものの、すごく怖くて……。

Q:本作は、新しい恐怖映画が求められている中で生まれた作品のようにも思います。現時点では未完成ですが、出演者としてはどのような印象を持ちましたか。
妻夫木聡(以下、妻夫木):やっぱり人間って、新しいものにすごく敏感で欲深いものだなあと。例えば世界中で人気の海外ドラマ「ウォーキング・デッド」シリーズも、ゾンビより人間が怖いという話になっている。求められているものも単純に消化しやすいものではなく「自分たち人間はどうあるべきなのか」というような、答えがなく死ぬまでずっと考え続けていかなければいけない人間の業みたいなところに、焦点が段々合ってきているのかなと。今回は中島監督としてもホラーを撮りたかったわけではないと思うのですが、イメージとして一般的には“怖い=ホラー”だと思われがちですよね。でも、形として今回の作品を実際に観ていただいた時に、今の人たちがどう思うのかということを、僕自身も知りたいと思っています。

岡田:ジャンルがカテゴライズされて、人気のあるものに集中しやすい中、それを壊してジャンルフリーになるものをどうやって作っていくのかを、作り手側が問われている時代だと思います。本作で描かれているような人間らしさや業というものは、誰もが楽しめるものだと思いますし、監督ご自身が世間や物事を真っ直ぐ見ていない方だと思うので……って言うと怒られちゃうかもしれませんが(笑)、中島監督がやりたかったのはホラーではなく、あくまで人間の怖さなのかなと思っています。
妻夫木:ホラーの在り方も、段々と“貞子”みたいな存在より、もっとリアルになってきているのかなと。形の見えるものよりも見えないものの方が、一層怖かったりするのかなという気がします。
監督から求められたのは不安定さ
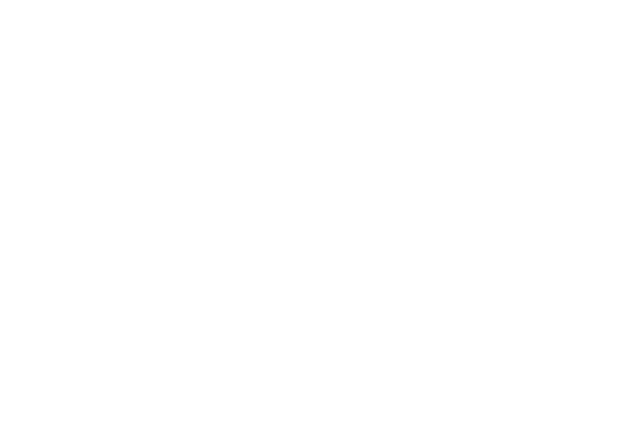
Q:岡田さんが演じたオカルトライターの野崎は、一見粗雑に見えながら、実はあるトラウマを抱えた複雑な人物でしたが、特に意識されたことは?
岡田:最近は、いわゆる強いイメージの役柄を求められることも多かったのですが「そういうのじゃない役をやりたいんでしょ?」というようなことを監督がおっしゃって、自分の中にある力みをとってくださったので、純粋に芝居を楽しんで役の一人として使われる喜びがありました。自分が表現する上で正解を探ったり、こうしたいと考えたり、明確な意図を求められることも多いですが、曖昧なままでいいというか「ボヤっとしたまま現場に来て、ボヤっとしたまま帰ってOK」といったような流れが、どこか中島監督にある気がして(笑)。もちろん監督の中での正解の画があるので、それにハメてほしいとは言われますが、僕ら男性陣にはむしろ、不安定さや不確定なことが求められていたのかなと思っています。とにかく台本がしっかりしてて、そのまま役に入り込むことができたので、芝居できるのが毎日楽しかったですね。
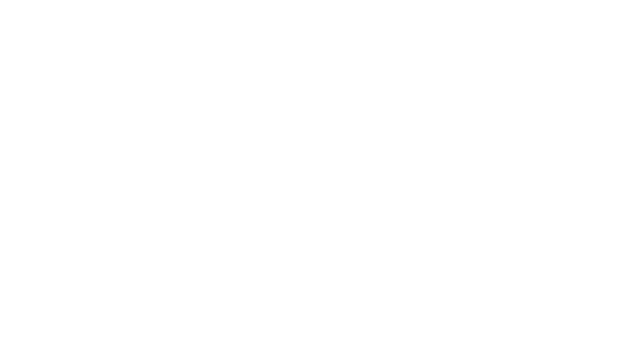
Q:イクメンパパの田原を演じた妻夫木さんは中島監督とは3作目で、前作『渇き。』に続いてひょうひょうとした、共感を得にくい役柄を演じていますが、求められているご自分の役回りをどのように感じていますか。
妻夫木:役者としての僕で遊んでくれている、ということだと思うので、すごく嬉しいですね。監督が、根本的な僕自身の性格を役柄と同じようにとらえているとしたら、殺意を覚えますけど(笑)。『渇き。』の時もそうでしたが、基本的には「面白いことやって」というような大雑把なことしか言われないんです。ハッキリ覚えている演出は、カラオケを歌うシーンでキーを下げようとしたら、「声が出ないのを一生懸命に歌っている方がいい」と言われて、何回もキーが高いまま歌わされたことくらい(笑)。今回の役柄としては、人間としての薄っぺらい軽さみたいなものを出したくて、普段もそれを意識していたので、この撮影期間中は多分そんな感じの人間になっていたはずです(笑)。

男性陣が放置されていた理由を推測
Q:中島監督はものすごくこだわりの強い方だけに、演出も細かいのかと思っていたのですが、キャラクターの説明などもなかったのでしょうか。
岡田:女性陣には「このタイミングで飲んでほしい」「この角度を向いてほしい」といった具合に、すごく演出が細かかったのですが、僕らは基本的に放置されていたので(笑)、その場その場の芝居を楽しむ感じでした。男性だけのシーンは、一回だけ本番をやってあっという間に終わることが多くて(笑)。衣裳合わせの時も、僕からは特に意見することはなかったので、衣裳を見て監督がイメージしているのはこういう感じの役なんだと感じていました。あとは「ヒゲ6ミリで、髪の毛はこれ。じゃあ現場で!」と言われて、監督と次にお会いしたのは撮影当日といったような感じでした。ホンの読み合わせもなですし。

妻夫木:あ、一回あったよ。確か(妻役の黒木)華ちゃんとの芝居の感じを見たいと言われて、ムネ(友人役の青木崇高)と3人で。中島監督もホン読みをやったのはほぼ初めてらしく、「もう二度とやらない」とか言ってたけど(笑)。ホン読みの時に言ったことを忘れて、本番では全く違うことを言ってきたので、本当に必要なかった(笑)。多分、その時々にやっていることがすべてだから、すごく直感的に動いている方なんだろうね。
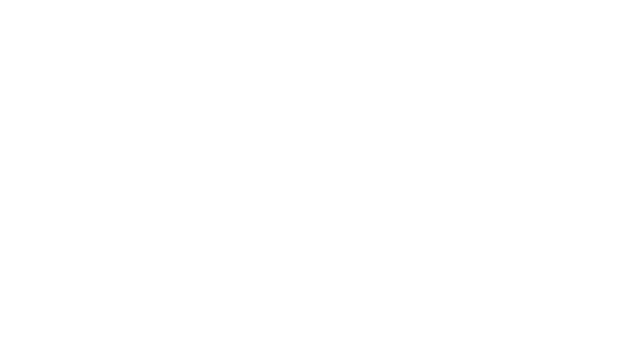
岡田:空っぽでいこうと思える監督というか、それを信頼とも才能に惚れているとも言えるかもしれないけど、中島監督の中ではすべて決まっている感じがあるし、いい台本もあるので、この方が監督だったら台本を読み込んでいけば、何とかしてくれるだろうという安心感があるよね。
妻夫木:撮影中はアドレナリンが出まくっているのか、全く寝ないで撮り続けることができる監督だから、深夜でも朝イチでも、難しいシーンの途中から段取りなしでいきなり「ハイ、スタート」と始めてしまうし、前後のシーンとのつながりなど細かいところを考えるのは(キャストやスタッフに)「あんたたちでお願いよ」といったおまかせなところもあって、大変なことも多いです。でも、それが結構楽しいですし、やっぱり信じてやっていると、編集もとにかく上手な方なので、本当に面白い作品に仕上げてくれる。だから岡田君の言う通り、僕たちはできるだけ空っぽの状態で現場に行って、いつでも監督の色に染まれた方が、登場人物一人一人の個性がハッキリと出る。それぐらい脚本が群像劇としてうまく成り立っているので、余計なことをしない方が、物語を壊さないことにつながると思うんですよね。
岡田:幸せな現場ですよね。
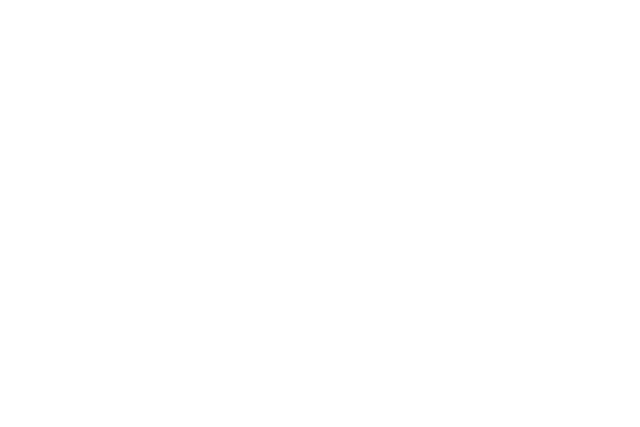
現代ならではのカオスがさく裂する中島ワールド

Q:お互いに撮影をご覧になっていないシーンも多いと思いますが、完成品で特に楽しみにしているシーンは?
妻夫木:岡田君の演じた野崎がいろいろ背負っているものがある中で、彼自身がラストの方で登場人物のいろんなことを受けていきながら、成長まではいかなくても変わっていく部分があると思うんです。その中で、この映画自体がどういう結末に向かっていくのかが気になっています。出演していながら、僕自身も謎なところが多いので(笑)。
岡田:僕も自分が出ていないところの方が楽しみですね。いい笑顔に見えていたはずが違うように見えていくキャラクターなど。あとは、やっぱりクライマックスの大掛かりなお祓いのシーンでしょうか。中島監督も「『面白いLIVEを観たな』と思ってもらえたらいい」とおっしゃっていたようですけど、現代だから起こりうる混沌)と言いますか、人間の願いや思い、いいものと悪いもの、いろんな宗教やエネルギーが混ざり合っている感じを日本映画で作ることができるのは、中島監督ならではの面白さだと感じています。

2002年の岡田主演のテレビドラマ「木更津キャッツアイ」の最終話に妻夫木がゲスト出演して以来の共演だという二人だが、約20年にわたって同時代で活躍し続けてきただけに、同世代として同じものを見て、経験してきた者同士ならではの深いシンパシーやたくましさが感じられた。また、作品の恐ろしい内容とは裏腹に終始笑顔の絶えない様子に、本作への確かな手応えと自信が窺えた。
映画『来る』は12月7日より全国東宝系にて公開
(C) 2018「来る」製作委員会


