ONE PIECE映画はなぜこれほど人の心をアツくするのか?

1999年からスタートした「ONE PIECE」のテレビシリーズは今年で20周年を迎え、8月9日には20周年記念作品となる3年ぶりの劇場版、第14作『劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』』が公開される。ここでは「なぜ『ONE PIECE』映画はこれほど人の心をアツくするのか?」という問いについて、いくつかの作品を取り上げながら考えてみたい。(大山くまお)
3つに分かれる『ONE PIECE』映画

全世界で4億5,000万部(2019年3月時点)を超えた、もはや説明不要の国民的コミック「ONE PIECE」の魅力は明快だ。「友情・仲間」を軸にしたテーマ、激しいアクションと小気味いいギャグ、力強い大きな物語と張り巡らされた伏線、熱いキャラクターたちによる熱い言葉……。爽快感があり、驚きがあり、感動がある。では、それらの魅力は、映画にどのように反映されているのだろうか。
これまで13作品が公開された『ONE PIECE』映画は、大きく3つに分けられる。
まず2000年に公開された記念すべき第1作『ワンピース』から第3作『ワンピース 珍獣島のチョッパー王国』(2002)まで。これらは「東映アニメフェア」の1作として公開されており、上映時間も60分以内の中編だ。いずれもテレビシリーズの合間のサイドストーリー的な作品であり、それぞれ「ONE PIECE」の魅力であるアクションとギャグが詰め込まれている。

第1作から第3作までが「東映アニメフェア」期とするなら、初の長編である第4作『ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険』(2002)から、第9作『ONE PIECE ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』(2008)までの6作品は「THE MOVIE」期。オリジナル要素の強いサイドストーリー(設定が微妙に違うのでパラレルワールドとも言える)もあれば、原作で人気の高いエピソードの映画化もあり、バラエティー豊かである。

そして第10作『ONE PIECE FILM ワンピースフィルム STRONG WORLD』(2009)から第13作『ONE PIECE FILM GOLD』(2016)までの、フルCG作品の第11作『ONE PIECE ワンピース 3D 麦わらチェイス』(2011)を除いた、3作品は、いずれもタイトルに「FILM」という刻印が打たれている。これらは原作者の尾田栄一郎が製作総指揮、総合プロデューサーとして深く関わった。それまではコンスタントに1年に1本ずつ作られてきたが、「FILM」期になると3~4年に1本となる。グッと溜めてドカンと放つ「ゴムゴムの巨人の銃(ギガントピストル)」のような作品群と呼んでいいだろう。
奇跡の作品『STRONG WORLD』
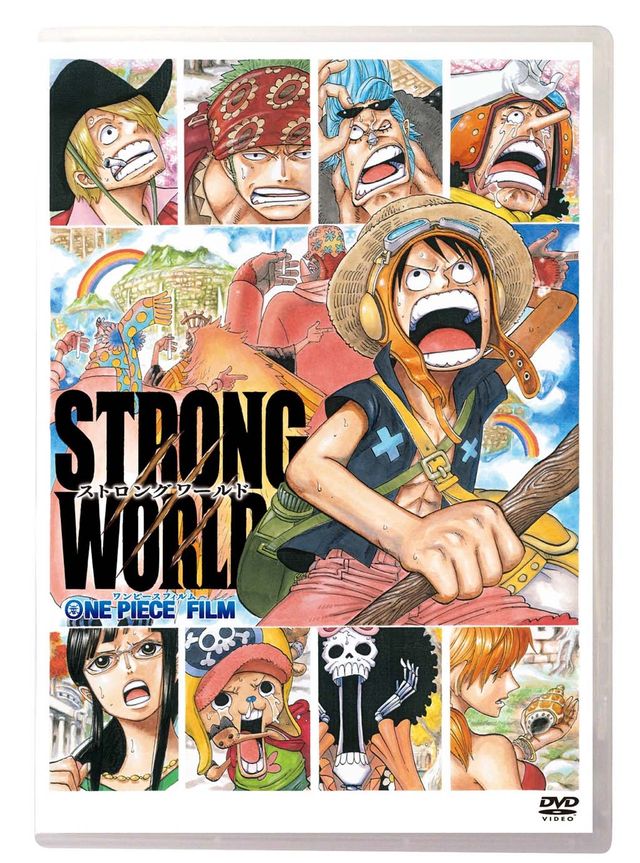
「一番デカかったのは、『STRONG WORLD』という映画をやったとき。あのときに意味のわからない爆発力が起きたんですよね。いろんな奇跡が重なって」
最初に挙げたいのは『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』(境宗久監督)だ。先の言葉は、原作者・尾田栄一郎によるもの。自らストーリーを書き下ろしたものの一度書いたストーリーを全ボツにして公開が9か月も延期になったり、決まるかどうかわからなかったMr.Childrenの主題歌が本当に決まったり、前売り券の印刷が間に合わないほど売れまくったりと、まさに「いろんな奇跡」が重なり、シリーズ最高(当時)の興行収入48億円を叩き出した。前作『ONE PIECE THE MOVIE エピソードオブチョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜』の興行収入が9.2億円だったことからも、本作が桁違いのヒット作だったことがわかる。
筋立ては極めてシンプル。残虐非道なボスキャラ“金獅子のシキ”が巨大な空飛ぶ島船に乗って現れたかと思えば、いきなり海軍の軍艦を空からドカドカ落としまくるというインパクト抜群のアバンタイトルから、ルフィがいきなりダイブしたかと思うと、森のクリーチャーたちに次々と襲われるというオープニングからエンディングまで、圧倒的アクションで押しまくる。

映画館のスクリーンの巨大さを存分に活かした構図が随所に見られ、荒々しいタッチで画面狭しとばかりに繰り出されるルフィの必殺技は説得力抜群。さらに敵も味方もいちいち大見得を切るものだから高揚感がすさまじい。複雑なストーリーや緻密な伏線は脇に置いておいて、原作が持つケレン味をこれでもかと押し出した、爆発力満点の作品だった。
シリーズ最高興行収入を記録した『ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット』(2012)、続く『ONE PIECE FILM GOLD』(2016)も勢いと迫力で押しまくる、劇場に特化したエンターテインメント作品だと言えるだろう。特にミュージカル風に始まる『GOLD』のド派手なオープニングは2D上映より3D上映、3D上映より4D上映のほうがヤバいという評判が巻き起こった。
涙なしには見られない『冬に咲く、奇跡の桜』

原作の初期の頃をこよなく愛するファンに支持されている『ONE PIECE』映画といえば、「ドラム王国編」をベースに原作者の尾田自らがアレンジを施した『ONE PIECE ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』(志水淳児監督)だろう。トニートニー・チョッパーをフィーチャーした(ポスターアートもチョッパーがメイン)この作品をひと言で表すなら「とにかく泣ける」。
“化け物”と蔑まれて人とかかわることができなかったチョッパーが、Dr.ヒルルク、Dr.くれは(ドクトリーヌ)、ナミたちの優しさによって徐々に心がほどけていき、最後はルフィに強引に誘われて仲間になる。チョッパーを突き放した後、過去を思い出して号泣するヒルルク、自決する直前に「まったく!!!! いい人生だった!!!!」と叫ぶヒルルク、「うるせェ!!! いこう!!!!」とルフィの叫びを聞いてヒルルクの笑顔を思い浮かべて号泣するチョッパーなど、名シーン、名台詞の釣瓶撃ちで涙腺が崩壊した観客も多い。

一方、シリーズ屈指の異色作として知られるのが『ONE PIECE ワンピース オマツリ男爵と秘密の島』(2005)。『サマーウォーズ』(2009)、『未来のミライ』(2018)などで知られる細田守監督の長編監督第1作である。
「史上最大の笑劇!!」とキャッチコピーがつけられたがコメディー要素は少なく、『ONE PIECE』特有のダイナミックなアクションも多くはない。むしろ、物語が進むにつれて、ダークで重苦しい雰囲気が作品全体を覆い尽くしていく。何より「ONE PIECE」の根幹をなす「友情・仲間」を引き裂くのが悪漢・オマツリ男爵の最大の目的なのだ。しかも、オマツリ男爵は誰よりも仲間を愛した男であり、仲間を亡くした悲しみによって蛮行を繰り返していたのだ。哀しさと皮肉と狂気に満ちた大人向けの一作。『ONE PIECE』ファンからの評価はけっして高くはなかったが、一見の価値はある。

テレビシリーズの延長のような作品から、異端の作品が生まれ、原作ファンが涙する作品が生まれた。そしてド迫力のスペクタクルで観客を圧倒する作品群も生まれている。強力なキャラクターと普遍的なテーマがしっかりと支えながら、『ONE PIECE』映画は一つのところにとどまることなく、常に進化し続けている。それが、このシリーズの魅力なのかもしれない。


