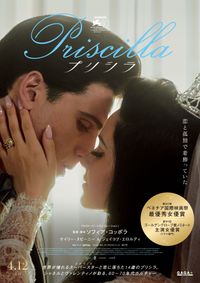ロバート・アルトマンやソフィア・コッポラが心酔した人妻の恋『逢びき』(1945年)
名画プレイバック

映画の主役は若く美しい男女と決まっていた1940年代、第二次世界大戦が終わろうとしている頃に作られた『逢びき』(1945)は、中年の男女がそれぞれ配偶者のいる身ながら惹かれ合う、いわゆる不倫の物語。医者と平凡な主婦の出会いから別れまでの数週間を巧みな構成で描き、『戦場にかける橋』(1957)や『アラビアのロレンス』(1962)で知られるデヴィッド・リーン監督の隠れた傑作だ。(冨永由紀)
映画はラフマニノフの「ピアノコンチェルト2番」とともに、主婦のローラ(セリア・ジョンソン)と医師のアレック(トレヴァー・ハワード)が逢瀬を重ねてきたロンドン近郊の駅の喫茶室から始まる。沈んだ表情で座っている2人の前を通りすがったローラの知人、ドリーが割り込んでくる。挨拶もそこそこに、彼女が一方的にまくし立てているうちにアレックは到着した汽車に乗るために立ち上がる。軽くローラの肩に手を添えると、ごく普通に立ち去る彼とローラにとって、それは今生の別れだった。もちろん、ドリーはそんなことを知る由もない。
ドリーと同じ汽車で帰路につくローラは、車中でも喋りっぱなしの知人の顔を見ながら「あなたが信頼できる、賢明で親切な友人なら良かったのに。ゴシップ好きのどうでもいい知り合いじゃなければ良かったのに」と心の中でつぶやく。とはいえ、詮索好きのドリーというキャラクターのおかげで、観客はアレックが翌週に南アフリカへ行ってしまうことなどをすんなりと知ることができる。けたたましい彼女に辟易して、ローラは「死ねばいいのに」と心の中で毒づいて、すぐに後悔する。映画はここから、誰にも打ち明けられない胸の内をありのまま真っ正直に語るローラの心の声とともに進んでいく。
家に戻ると、何の変哲も無い日常がそこにある。クロスワードパズル好きの優しい夫と、まだ幼い娘と息子がいる。何も知らずにパズルを楽しむ夫と居間で向かい合い、ローラはラフマニノフのピアノコンチェルトを流しながら、回想に耽っていく。毎週木曜日、買い出しに出かけては貸本屋で本を借りたり、映画を観たり、時には友人と食事して夕方に汽車で帰宅するのが習慣だった彼女とアレックの冒頭の駅での馴れ初めから街中での偶然の再会までは流れるようなテンポで描かれる。決して説明的ではないのに、状況を的確に把握させる自然な会話は原作の戯曲「Still Life」の著者であり、映画の製作、及び共同脚本を手がけたノエル・カワードによるもの。主役2人の会話はもちろん、喫茶室を切り盛りする老婦人と駅員、若いウエイトレス、客たちのやりとりも生き生きとしている。ヒロインの気持ちの高まりをロマンティックに盛り上げるラフマニノフを選曲したのもカワードだ。
ローラとアレックは3度目の偶然の再会でようやく名乗り合う。昼食を共にしても、チップまで割り勘にするほど色気のない関係だが、一緒に映画を観て、お茶を飲みながら仕事への情熱を語るアレックの話に聞き入るうちにローラは一気に恋に落ちる。目をとろんとさせて、うっとり聞き入る表情はまるで少女のようだ。熱心に話を聞いてくれる女に、男の気持ちも大きく動き、「来週も会えますか」と誘う。
通信事情が当時と全く違う現代において、人と人が待ち合わせで行き違うことは不可能に近い。だが、昔は約束した時間に落ち合えなければ、相手に何かあったのではないかと心配し、場合によっては2度と会うこともできなくなることもあった。だからこそ、行き違った相手と偶然に再会できれば、そこに深い意味や運命を感じるのは当然のことだろう。そんな事態も経験した2人はさらに盛り上がり、越えてはいけない一線を踏み越えようとするのだが……。
セリア・ジョンソンは貞淑な表情を保ったまま、揺れ動く心や悲しみを目だけで表現する。表面上は抑えた演技だが、ナレーションの声はその分、感情豊かで、そのコントラストも非常に効果的だ。70年前、30代半ばの女性は今の感覚でいえば、もはやおばあさんに近い。もう若くないことを自覚している地味な女性をそのまま描き、にもかかわらず、深い共感を抱かせたのは画期的だったと言えるだろう。多くの映画人に愛されている作品だが、ロバート・アルトマンは若い頃、暇つぶしに入った映画館で観た時のことを妻にこう語ったそうだ。「主役はグラマラスじゃなく、美人でもない。なんでこんな映画を観ているのかと思っていたが、20分後には泣いていた。彼女に恋をした」。後に『第三の男』(1949)やリーン監督の『ライアンの娘』(1970)にも出演しているトレヴァー・ハワードは本作が初の大役。清潔感と慎みのある俳優2人ゆえに、不倫を扱いながらも生々しさではなく、不器用で生真面目な男女の苦悩が胸に迫る。終盤でもう一度繰り返される冒頭の駅のシーンには、最初に観た時には気づかない多くのものが込められている。
平穏な家庭に恵まれ、愛されてもいるのに、それでも人は孤独を感じてしまうことがある。そんな孤独を抱えた者同士が出会い、長い人生のほんの一瞬を共に過ごす。時代は変わっても普遍的な感覚はいつの時代も人の心を捉え、1980年代にはロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープ主演で、まるで本作の変奏曲のような『恋におちて』(1984)が作られ、ソフィア・コッポラは、『ロスト・イン・トランスレーション』(2003)は本作に大きな影響を受けて作ったと語っている。
ローラの回想は、パズルに興じる夫に話しかける体だ。その言葉の端々から彼女の結婚がいかに恵まれたものなのかがわかる。最も信頼できる、親切な人間を、彼女は裏切っている。ローラは夫について、「中背で茶色の髪。優しくて感情的ではなくて、全くデリケートじゃない」と知り合ったばかりの頃、アレックに説明していた。毎週、買い物に出かけた木曜に決まって帰りの遅い妻を毎回ごく当たり前のように迎えてきた鷹揚(おうよう)なこの夫こそ、実に興味深い存在だ。明らかに心ここにあらずの状態だった妻を、この夫はどのように見ていたのか。それは映画を観ていても全くわからない。アレックとの恋で頭がいっぱいだった数週間、ローラの眼中になかったことだからだ。実は夫の想像を超えるようなことが起きていた。いや、彼は本当に何も気づいていなかったのだろうか。彼は、具体的なことを突き止めようとはせずとも妻の悲しみを察知する。そして「遠くに行っていたんだね。帰ってきてくれて、ありがとう」と言い、2人は抱き合う。その後に現れる「THE END」という文字は、なぜかとても残酷に思えるのだ。