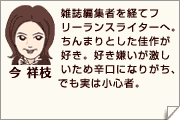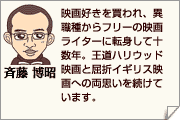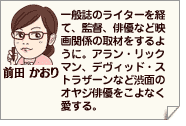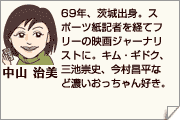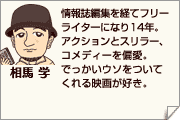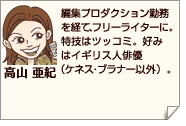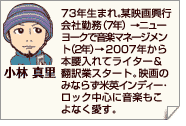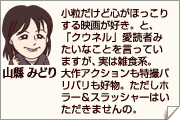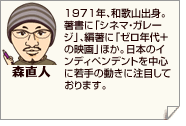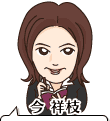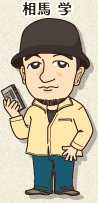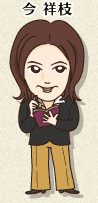サードシーズン2012年6月
私的映画宣言
ゴールデンウイークから3週間ほど久々のゴーストライター業で自宅に引きこもり。しかも新しい炊飯器で炊く熊本県産山村産の米がおいしくて、いつの間にかおなかに……。とにかく痩せなきゃ。
●6月公開の私的オススメは、『星の旅人たち』(6月2日公開)と『キリマンジャロの雪』(6月9日公開)。どちらも本当に心に染みますよ。
6月公開作品の劇場用パンフレットのお仕事を立て続けにこなす日々。いろいろ調べてみると、最初は普通に面白い……程度だった映画に、どんどん愛着が湧いてくる。映画は奥が深いと、改めて肝に銘じた次第。
●6月公開の私的オススメは、その中の一つ『幸せへのキセキ』(6月8日公開)。
『少年は残酷な弓を射る』のエズラ・ミラーに幸運にも2度も取材。映画と違って、素顔はむちゃくちゃ人懐っこくて好青年。「救命医ハンク セレブ診療ファイル」に数話出演していたのだが、「あんまり役が違うからか、だーれも気付いてくれない」と笑っとりました。確かに……。
●6月公開の私的オススメは、『ファウスト』(6月2日公開)。
録画してあった「オペラ座の怪人 25周年記念公演 in ロンドン」をやっと観る。シエラ・ボーゲス(ブロードウェイ版やや珍作「リトル・マーメイド」)が好みでなく残念。でもカーテンコールの歴代ファントム競演が素晴らしくコルム・ウィルキンソンの歌声が聴けて感激! 舞台版の当たり役「レ・ミゼラブル」の映画版にも出演で楽しみ。
●6月公開の私的オススメは、『星の旅人たち』(6月2日公開)。
 スノーホワイト
スノーホワイト
世界中で愛されているグリム童話「白雪姫」を大胆にアレンジした、白雪姫と女王が死闘を繰り広げるアドベンチャー。戦術とサバイバル術を身に付けた白雪姫ことスノーホワイトには『トワイライト』シリーズのクリステン・スチュワートがふんし、『モンスター』のシャーリーズ・セロン、『マイティ・ソー』のクリス・ヘムズワースが共演。メガホンを取るのはCMディレクター出身のルパート・サンダース。オリジナリティーを加えたストーリーはもちろん、白雪姫の斬新なイメージを演出するスタイリッシュな映像やファッションも要チェックだ。
[出演] クリステン・スチュワート、シャーリーズ・セロン
[監督] ルパート・サンダース
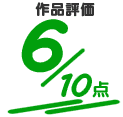 美貌を武器に生きてきた女性が見たら切実さが増しそうな物語。シャーリーズ・セロンが『モンスター』以上の不細工&老けメイクにチャレンジしているけど、美人だから怖くないのよね。腐ってもタイならぬ、腐っても美人! 美と永遠の若さに固執したら魔女になって、最終的には心が清らかな女性に負けるという教訓もあるけど、ピュアな心の持ち主であるスノーホワイトも美人なんだよね(クリステンのウサギみたいな前歯がかわいい!)。美人vs.美人じゃないと結局、つまんないってことか。ま、いいけど。ファンタジー部分の特撮はかなり素晴らしく、特に邪悪な森のおどろおどろしたモノノケ感には「おおっ」と感動。女優が素晴らしいので男優が刺身のツマみたいに見えるのがちょっと残念だったかも。
美貌を武器に生きてきた女性が見たら切実さが増しそうな物語。シャーリーズ・セロンが『モンスター』以上の不細工&老けメイクにチャレンジしているけど、美人だから怖くないのよね。腐ってもタイならぬ、腐っても美人! 美と永遠の若さに固執したら魔女になって、最終的には心が清らかな女性に負けるという教訓もあるけど、ピュアな心の持ち主であるスノーホワイトも美人なんだよね(クリステンのウサギみたいな前歯がかわいい!)。美人vs.美人じゃないと結局、つまんないってことか。ま、いいけど。ファンタジー部分の特撮はかなり素晴らしく、特に邪悪な森のおどろおどろしたモノノケ感には「おおっ」と感動。女優が素晴らしいので男優が刺身のツマみたいに見えるのがちょっと残念だったかも。
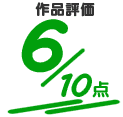 ダークな映像の中で童話のヒロインを戦わせるアイデアは、さながらゴス版『アリス・イン・ワンダーランド』。しかし、それ以上の驚きがあるわけではなく、たくましいヒロイン像がドラマ的に生かされているとは言い難い。ヘムズワースふんするハンターのキャラクターは、もう少し生かしようがあったのでは。絶叫連発のシャーリーズ・セロンの怪演や、7人の森の番人にふんする英国演技派俳優陣の頑張りなど、むしろ脇キャラに妙味アリ。
ダークな映像の中で童話のヒロインを戦わせるアイデアは、さながらゴス版『アリス・イン・ワンダーランド』。しかし、それ以上の驚きがあるわけではなく、たくましいヒロイン像がドラマ的に生かされているとは言い難い。ヘムズワースふんするハンターのキャラクターは、もう少し生かしようがあったのでは。絶叫連発のシャーリーズ・セロンの怪演や、7人の森の番人にふんする英国演技派俳優陣の頑張りなど、むしろ脇キャラに妙味アリ。
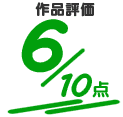 戦う白雪姫というアイデアは悪くないが、原作を中途半端に改変してしまったため、結果的にアクション映画として成立していないのが残念。カタルシスのない最終決戦はあっけなく、ばたばたと唐突にエンディングを迎える(撮影途中で予算切れになったのか?)。ラブストーリーも宙ぶらりんでドラマも盛り上がらず。特典映像的に挿入される妖精たちのファンタジー・ワールドも撤収が早いこと。のっぺらぼうのシルバーサーファーみたいなやつと白鹿はかっこいいです。
戦う白雪姫というアイデアは悪くないが、原作を中途半端に改変してしまったため、結果的にアクション映画として成立していないのが残念。カタルシスのない最終決戦はあっけなく、ばたばたと唐突にエンディングを迎える(撮影途中で予算切れになったのか?)。ラブストーリーも宙ぶらりんでドラマも盛り上がらず。特典映像的に挿入される妖精たちのファンタジー・ワールドも撤収が早いこと。のっぺらぼうのシルバーサーファーみたいなやつと白鹿はかっこいいです。
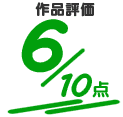 正直、白雪姫が闘うなんて……と思ったが、暗い森の何とも恐ろしい画作りにゾクゾク。悪夢を見ちゃいそうなぐらい不気味。想像力を刺激してくれる映像センスが素晴らしい。主演のクリステン・スチュワートもドレスより甲冑姿が似合う。立派な体躯のクリス・ヘムズワースが姫を守る役というのも適役。悪の女王シャーリーズ・セロンが老いを恐れてヒステリックを起こすわ、若い娘の生気を吸い取るわ、ハマリすぎていてマジ怖い。でも一番、ぜい沢なのは森の番人のキャスト。いや、これはこれは……。本当に観ていて楽しくなった。
正直、白雪姫が闘うなんて……と思ったが、暗い森の何とも恐ろしい画作りにゾクゾク。悪夢を見ちゃいそうなぐらい不気味。想像力を刺激してくれる映像センスが素晴らしい。主演のクリステン・スチュワートもドレスより甲冑姿が似合う。立派な体躯のクリス・ヘムズワースが姫を守る役というのも適役。悪の女王シャーリーズ・セロンが老いを恐れてヒステリックを起こすわ、若い娘の生気を吸い取るわ、ハマリすぎていてマジ怖い。でも一番、ぜい沢なのは森の番人のキャスト。いや、これはこれは……。本当に観ていて楽しくなった。
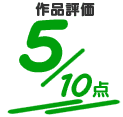 根が意地悪そうなシャーリーズ・セロン、透明感のあるクリステン・スチュワート共に役のイメージを損なわず説得力のある美貌は観ていて楽しい。ただ、元ネタとの物語のリンクのさせ方がイマイチうまくなくて、なぜこれが「白雪姫」である必要があるのかがわからない。スノーホワイト=救世主の図も唐突感が拭えず感情移入できず、まだ継母の方がキャラとしては魅力的で男性陣は印象が薄すぎる。最初から次作に続けるためのラストの引っ張りも極めてストレスフル。
根が意地悪そうなシャーリーズ・セロン、透明感のあるクリステン・スチュワート共に役のイメージを損なわず説得力のある美貌は観ていて楽しい。ただ、元ネタとの物語のリンクのさせ方がイマイチうまくなくて、なぜこれが「白雪姫」である必要があるのかがわからない。スノーホワイト=救世主の図も唐突感が拭えず感情移入できず、まだ継母の方がキャラとしては魅力的で男性陣は印象が薄すぎる。最初から次作に続けるためのラストの引っ張りも極めてストレスフル。
 愛と誠
愛と誠
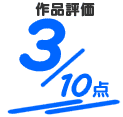 人気テレビシリーズ「Glee」路線を狙ったのか? でも『愛と誠』でそんなことする必要ないよね。業界内に監督の熱狂的なファンがいて、「遊び心満載」「三池さんらしいセンス!」なんて褒めている人もいるけど、内輪受けしているだけとしか思えない。実際に試写室で大笑いしている人もいなかったし、監督がそういう声を真に受けるとしたら単なる裸の王様でしょう。いや笑えるシーンはいくつかあるのよ。伊原剛志演じる不良とか安藤サクラの頑張りとか。本筋とはまったく関係ないし、笑えるスケッチを積み上げていって最後にドカンと笑わせるなんて展開でもなし。本当にがっかりさせられた。
人気テレビシリーズ「Glee」路線を狙ったのか? でも『愛と誠』でそんなことする必要ないよね。業界内に監督の熱狂的なファンがいて、「遊び心満載」「三池さんらしいセンス!」なんて褒めている人もいるけど、内輪受けしているだけとしか思えない。実際に試写室で大笑いしている人もいなかったし、監督がそういう声を真に受けるとしたら単なる裸の王様でしょう。いや笑えるシーンはいくつかあるのよ。伊原剛志演じる不良とか安藤サクラの頑張りとか。本筋とはまったく関係ないし、笑えるスケッチを積み上げていって最後にドカンと笑わせるなんて展開でもなし。本当にがっかりさせられた。
 ノスタルジックなミュージカル・コメディー、純愛ドラマ、トンデモ映画などなど、さまざまな形容詞が思い付くのだが、どれもがこの作品を正確に言い当てていない歯がゆさ。正直、どう表現していいのか迷う。あえて最もツボにハマったポイントを挙げるなら、熱い愛と冷めた誠が醸し出す温度差のおかしさ。そこにありがちなドラマツルギーを笑い飛ばす風刺を見ることも可能だが、この際、小難しいことはどうでもいい。黙って観るべし!
ノスタルジックなミュージカル・コメディー、純愛ドラマ、トンデモ映画などなど、さまざまな形容詞が思い付くのだが、どれもがこの作品を正確に言い当てていない歯がゆさ。正直、どう表現していいのか迷う。あえて最もツボにハマったポイントを挙げるなら、熱い愛と冷めた誠が醸し出す温度差のおかしさ。そこにありがちなドラマツルギーを笑い飛ばす風刺を見ることも可能だが、この際、小難しいことはどうでもいい。黙って観るべし!
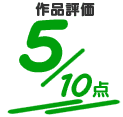 過激な青春ラブコメだが、一応ミュージカル映画。といっても三池監督の過去作『カタクリ家の幸福』とは性質が異なる。ウケを狙ったおふざけミュージカルで、歌も踊りも物足りない。ミュージカル・シーンになると突然白けてしまうのだ。オフビートなユーモアも上滑りでほとんど笑えないし、アニメ・パート(特に最後)は蛇足。巨大ずた袋は『オーディション』をほうふつさせられて、ぐっと来たけど(中の人は大杉漣ではなく武井咲だ)。
過激な青春ラブコメだが、一応ミュージカル映画。といっても三池監督の過去作『カタクリ家の幸福』とは性質が異なる。ウケを狙ったおふざけミュージカルで、歌も踊りも物足りない。ミュージカル・シーンになると突然白けてしまうのだ。オフビートなユーモアも上滑りでほとんど笑えないし、アニメ・パート(特に最後)は蛇足。巨大ずた袋は『オーディション』をほうふつさせられて、ぐっと来たけど(中の人は大杉漣ではなく武井咲だ)。
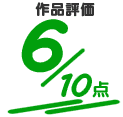 梶原一騎原作のベタな純愛劇画を、平成版「ウエスト・サイド物語」に。何でもアリな三池作品とはいえ、アニメも加えていつも以上にコッテコテ。アナクロな匂いがむせ返る中で、武井咲のブリッコぶりも意外なほどハマっている。が、おいしいところを持っていったのは、「おっさんにしか見えない病」に悩む学ラン姿の伊原剛志。最近、渋みを増しつつあるのに「狼少年ケンの歌」を歌うシーンは切ないなー。ほか劇団四季の輝かしいキャリアをのぞかせる市村正親の足の上がりっぷりにもびっくり。何にせよ、怖いモノ見たさで楽しむ見世物小屋的作品だと思う。
梶原一騎原作のベタな純愛劇画を、平成版「ウエスト・サイド物語」に。何でもアリな三池作品とはいえ、アニメも加えていつも以上にコッテコテ。アナクロな匂いがむせ返る中で、武井咲のブリッコぶりも意外なほどハマっている。が、おいしいところを持っていったのは、「おっさんにしか見えない病」に悩む学ラン姿の伊原剛志。最近、渋みを増しつつあるのに「狼少年ケンの歌」を歌うシーンは切ないなー。ほか劇団四季の輝かしいキャリアをのぞかせる市村正親の足の上がりっぷりにもびっくり。何にせよ、怖いモノ見たさで楽しむ見世物小屋的作品だと思う。
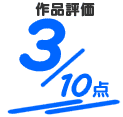 三池監督がやりたいこと、企画自体は非常に面白そうと個人的には思っていたので周囲の散々な悪評を聞くも興味津々で観に行った。が、話題のパフォーマンスは音楽もアレンジもうまいもヘタウマも振り付けもあまりにも中途半端。物語はもはやどうでもいいが、おおっと楽しみかける瞬間があっても続かず、だらだらと無駄に長くゆるゆるな演出はむなしく疲れた。三池さんだからもっと突き抜けたカルトを期待した自分を猛省。やるならやりきってよ!
三池監督がやりたいこと、企画自体は非常に面白そうと個人的には思っていたので周囲の散々な悪評を聞くも興味津々で観に行った。が、話題のパフォーマンスは音楽もアレンジもうまいもヘタウマも振り付けもあまりにも中途半端。物語はもはやどうでもいいが、おおっと楽しみかける瞬間があっても続かず、だらだらと無駄に長くゆるゆるな演出はむなしく疲れた。三池さんだからもっと突き抜けたカルトを期待した自分を猛省。やるならやりきってよ!
 少年は残酷な弓を射る
少年は残酷な弓を射る
イギリスの女性作家に贈られる文学賞として著名なオレンジ賞に輝く、ライオネル・シュライバーの小説を映画化した家族ドラマ。息子がとある事件を起こしたことを機に、それまでの彼と自身の向き合い方を見つめ直し、悩み抜く母親の姿を静謐(せいひつ)かつ重厚に映し出す。『フィクサー』のティルダ・スウィントンが、苦悩する母親にふんするだけでなく、製作総指揮も担当。メガホンを取るのは『モーヴァン』で注目を集めた、リン・ラムジー。衝撃的展開と殺伐としたムードに圧倒されるだけでなく、親と子の関係についても深く考えさせられる。
[出演] ティルダ・スウィントン、ジョン・C・ライリー
[監督] リン・ラムジー
 おなかを痛めて生んだわが子が愛してくれるのは当たり前という女性の思い込みをあっさりと蹴散らしてくれる。タイトルの少年ことケヴィンがとにかく邪悪。『オーメン』のダミアン以上に悪魔的で、母親をとことん毛嫌いし、純真な妹をひどい目に遭わせ……。「氏より育ち」派ではあるけど悪の魂を持って生まれる人もいるとは思っているので、ケヴィンの行動には特には驚かないが、息子を嫌悪することに苦悩する母親の姿に胸が痛む。息子を嫌いと思うこと自体が母にとっては罪悪なのか? 親子だから必ず愛し合えるって理想論のような気もするし、母子の関係について深く考えさせてくれる怪作だ。
おなかを痛めて生んだわが子が愛してくれるのは当たり前という女性の思い込みをあっさりと蹴散らしてくれる。タイトルの少年ことケヴィンがとにかく邪悪。『オーメン』のダミアン以上に悪魔的で、母親をとことん毛嫌いし、純真な妹をひどい目に遭わせ……。「氏より育ち」派ではあるけど悪の魂を持って生まれる人もいるとは思っているので、ケヴィンの行動には特には驚かないが、息子を嫌悪することに苦悩する母親の姿に胸が痛む。息子を嫌いと思うこと自体が母にとっては罪悪なのか? 親子だから必ず愛し合えるって理想論のような気もするし、母子の関係について深く考えさせてくれる怪作だ。
 エズラ・ミラーの悪魔のような上目遣いの怪演に、全身から疲労感を発するティルダ・スウィントンの熱演。それだけでもピリピリとした緊張感が伝わってきて十分にコワいのに、全編に氾濫する赤いイメージも妙にショッキング。ワイン、ペンキ、非常灯、ケチャップ、クレヨンなどなどの赤色にドキッとさせられる。こだわり抜いた色彩感覚は監督の映像センスの良さの表れか。血がほとんど出ないにもかかわらず、スプラッター映画レベルの衝撃!
エズラ・ミラーの悪魔のような上目遣いの怪演に、全身から疲労感を発するティルダ・スウィントンの熱演。それだけでもピリピリとした緊張感が伝わってきて十分にコワいのに、全編に氾濫する赤いイメージも妙にショッキング。ワイン、ペンキ、非常灯、ケチャップ、クレヨンなどなどの赤色にドキッとさせられる。こだわり抜いた色彩感覚は監督の映像センスの良さの表れか。血がほとんど出ないにもかかわらず、スプラッター映画レベルの衝撃!
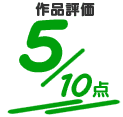 悪魔のような少年殺人鬼と母親の愛憎劇。とことん痛切でヘビーな作品ではある。少年の狂気を体現した醜悪な表情やしぐさは徹底しており、むしずが走った。が、そんなホラー・サスペンスに転がりそうなジャンル映画的要素をアート映画のフォームで昇華すると、表面的で空疎な映画にしかなり得ないことがわかる。怪物的な子どもとわかりあえない母親の苦悩はわかるが、同情はできない。彼女は最初から息子を愛していないのだから。息子を主役にして、心の闇の深遠に迫った方がまだよかった気がする。
悪魔のような少年殺人鬼と母親の愛憎劇。とことん痛切でヘビーな作品ではある。少年の狂気を体現した醜悪な表情やしぐさは徹底しており、むしずが走った。が、そんなホラー・サスペンスに転がりそうなジャンル映画的要素をアート映画のフォームで昇華すると、表面的で空疎な映画にしかなり得ないことがわかる。怪物的な子どもとわかりあえない母親の苦悩はわかるが、同情はできない。彼女は最初から息子を愛していないのだから。息子を主役にして、心の闇の深遠に迫った方がまだよかった気がする。
 始終、息子の顔色をうかがう母親に、彼女の心を見透かすような目で見る息子。『モーヴァン』もそうだったが、リン・ラムジー監督って、映像はクールでオシャレだけど、描くことはかなりエグくて、人の神経を容赦なく逆なでし、神髄を突いてくる。本作でも目を覆いたくなったり、気分悪っ! とつぶやきたくなるシーン多々。だが、悪魔の申し子のようでも、わが子ならいつかはわかり合えるといちるの望みを抱く母を演じるティルダが素晴らしい。そして、そのささいな思いを残酷なまでに打ち砕く息子役のエズラ・ミラーに、幼児期を演じた二人の子役たちが、ある意味、オーメン以上の恐ろしさでゾッとさせる。
始終、息子の顔色をうかがう母親に、彼女の心を見透かすような目で見る息子。『モーヴァン』もそうだったが、リン・ラムジー監督って、映像はクールでオシャレだけど、描くことはかなりエグくて、人の神経を容赦なく逆なでし、神髄を突いてくる。本作でも目を覆いたくなったり、気分悪っ! とつぶやきたくなるシーン多々。だが、悪魔の申し子のようでも、わが子ならいつかはわかり合えるといちるの望みを抱く母を演じるティルダが素晴らしい。そして、そのささいな思いを残酷なまでに打ち砕く息子役のエズラ・ミラーに、幼児期を演じた二人の子役たちが、ある意味、オーメン以上の恐ろしさでゾッとさせる。
 渇いたタッチで淡々と、恐ろしい事件の顛末(てんまつ)が明かされていく過程にはスリリングかつあらがい難い吸引力がある。全編を通して文句のつけようのない演技のティルダ・スウィントン演じるエヴァは、はたから見た隙のない完璧さはどこか危うさを感じさせて、こういう女性っているなあと思ってみたり。怖い怖い。新星エズラ・ミラーの怪物ぶりは生理的な不快さを感じさせつつ、内に秘めた残酷さがにじむ表情があやしく魅力があって適役だ。
渇いたタッチで淡々と、恐ろしい事件の顛末(てんまつ)が明かされていく過程にはスリリングかつあらがい難い吸引力がある。全編を通して文句のつけようのない演技のティルダ・スウィントン演じるエヴァは、はたから見た隙のない完璧さはどこか危うさを感じさせて、こういう女性っているなあと思ってみたり。怖い怖い。新星エズラ・ミラーの怪物ぶりは生理的な不快さを感じさせつつ、内に秘めた残酷さがにじむ表情があやしく魅力があって適役だ。