鬼才・深田晃司監督が見据えるアフターコロナ時代の映画界とは?
第33回東京国際映画祭
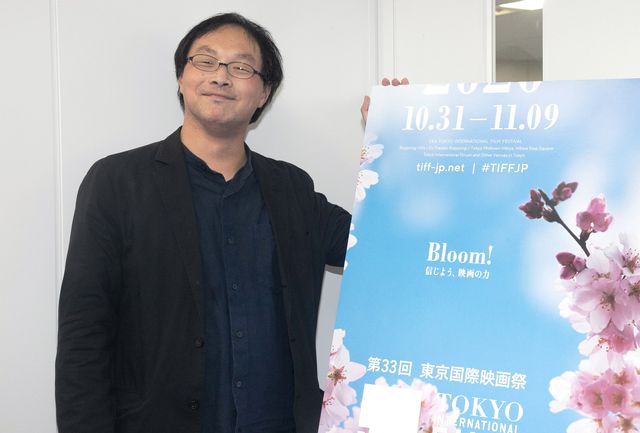
10月31日から開催される、第33回東京国際映画祭(以下TIFF)の「Japan Now 部門」では、「気鋭の表現者 深田晃司」と題した深田晃司監督作品の特集上映が行われる。今年は映画監督としてのみならず、「ミニシアターエイド基金」の立ち上げなどでも存在感を見せつけた深田監督。彼の目に見える日本映画界の現状、そして映画の未来とは何なのか?
『淵に立つ』が第69回カンヌ国際映画祭「ある視点部門」審査員賞を受賞するなど、海外での評価も高い深田監督。そんな彼が海外に飛躍するきっかけとなったのは、2010年の第23回TIFF「日本映画・ある視点部門」に出品された『歓待』が作品賞を受賞したことだった。深田監督も「やはり映画祭で賞を取ったことで、他国の映画祭に興味を持ってもらえたというのが非常に大きかった。映画祭は人と人との出会いの場であり、作家を後押しし、育てる場だということを自覚した瞬間でした」と振り返る。
今回の特集上映では、最新作『本気のしるし 《劇場版》』をはじめ、『よこがお』『淵に立つ』といった近年の作品を中心に、初長編作品『東京人間喜劇』、そして5本の短編を集めた短編プログラムなどが上映される。特に『東京人間喜劇』と、在宅で製作した短編映画『move / 2020』は深田監督が上映を熱望した作品で、「なかなか観られる機会がない作品を、TOHOシネマズで上映してもらえるのはうれしいです」と笑顔を見せる。
今回の特集について「2010年にTIFFで賞をいただいて。10年後の2020年にこうやって改めて呼んでもらえるということは自分にとってもいい節目になった」と語る深田監督は、「自分が作っている作品は自主映画の延長だと思っているんですが、この10年の間も、自分が作りたい作品を作り続けることができた。それは本当に恵まれていると思いますし、キャリアの今の段階で特集を組んでもらえるというのは、これから作る作品への期待が込められていると思う」。と今後も頑張ろうと気合を入れ直している様子だ。
今年は最新作『本気のしるし 《劇場版》』が、第73回カンヌ国際映画祭「オフィシャル セレクション2020」に選出されるなど、映画監督として注目を集めている。その一方で、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の影響により、閉館の危機にさらされている全国のミニシアターを救うための「ミニシアターエイド基金」を濱口竜介監督らと立ち上げるなど、映画業界に対する提言も積極的に行ってきた。
コロナ禍の映画業界の状況について、「今までうまくいっていた映画業界がコロナによってガタガタになってしまったのではなく、むしろコロナによって、これまでダメだった部分がよりあらわになったという言い方が正しい。だからアフターコロナの映画業界は、現状維持を目指すのでは駄目で、そもそも何が駄目だったのかということを何度でも問い直さないといけない」と指摘する。
さらに、日本映画界について「国家予算における文化予算の規模としては、フランスの8分の1、韓国の9分の1しかないような状態」と語る深田監督。「もともと日本にある文化予算は、年間およそ1,000億円。今回は560億円の補正予算がつきましたが、それでも韓国やフランスに比べるとまったく足りない状況。日本の芸術関係者は、本当に極端に少ない文化予算の中で活動しています。コロナ禍を機に、映画人も発言していかなければという意識が高まりましたが、業界内の連携はまだまだ不足しています。これに関しては本当に地道に情報発信を続け、対話をしていくしかないですね」と現状を分析する。
そんな情報発信のひとつとして、TIFF、東京フィルメックス、NPO法人独立映画鍋との共催企画となるシンポジウムも行われる予定だ。「去年は東京フィルメックスさんとの共催で映画の現場の労働環境の話をしました。今年はコロナ禍での映画祭の役割というテーマでシンポジウム(オンライン開催)を行います。多くの映画祭は、単に人を集めて映画を見せているだけではなく、映画のマーケットとしての高い公共性を担っています。そこで、業界の問題に対する啓発や、海外の映画人たちと話す場を設けることで、自分たちが当たり前だと思っていたことが、実は当たり前でないということを知ることができればと思います」と企画意図を語る深田監督。ミニシアターエイド基金設立を経て、改めてミニシアターの意義を世間に示すことができたからこそ、今後の恒常的な制度設計と支援の継続を訴えるきっかけになればとアピールした。(取材・文:壬生智裕)
第33回東京国際映画祭は10月31日から11月9日まで六本木ヒルズほかにて開催








