【ネタバレ】『ONE PIECE FILM RED』謎多き赤髪海賊団を描く挑戦 谷口悟朗監督が明かす裏話
『ONE PIECE FILM RED』(公開中)を手がけた谷口悟朗監督がインタビューに応じ、謎多き人気キャラクター・シャンクスと彼が率いる赤髪海賊団の描き方や、クライマックスの胸熱シーンについて語った。(以下『ONE PIECE FILM RED』の重大なネタバレを含みます)
【動画・ネタバレ】谷口監督が語るシャンクス&クライマックス インタビューの様子
■過去のシャンクスは完成していない

“歌声と赤髪”をテーマに、四皇・シャンクスの“娘”である世界的歌姫・ウタの物語を描く本作。『ONE PIECE』屈指の人気キャラクターでありながら、謎に満ちたシャンクスが劇場版に本格登場することは、公開前からファンの間で話題になっていた。
「シャンクスをきちんと描きたかった」と語る谷口監督は、シャンクス役の池田秀一に「キャラクターを構築し直していただいても、今までをベースに声を当てていただいても、そこは池田さんにお任せいたします」と伝えたという。「シャンクスは、どうしても絵として表情が一定のレベル以上強く出せない。しかし、表情が全くないと、観客は『彼は何を考えているのだろう?』と混乱してしまいます。それではよろしくない。なので、池田さんの声が観客を『こっちの方向性だよ』と導く役割を担っています。そういった部分を池田さんにお願いできたのはよかったです」
劇中では四皇の風格が漂う現在のシャンクス、ウタの父親らしく柔らかい表情を見せる12年前のシャンクスが登場するが、「過去のシャンクスは完成していない」と谷口監督は強調する。「海の男としても、シャンクスは完成しきっているわけではありません。彼が現在に至るまで、いろいろなことが起きて、いろいろなことを経験した結果、キャラクターは完成していくものだと思っています。池田さんにも、キャラクターのそういった流れは意識していただけると嬉しいですと伝えました」
■赤髪海賊団の登場「情報過多は避けたかった」

シャンクスやウタだけでは終わらず、海軍が「最もバランスのいい鉄壁の海賊団」として警戒する赤髪海賊団の本格登場もファンを熱狂させている。副船長のベン・ベックマン、ウソップの父親のヤソップはもちろん、ラッキー・ルウ、ライムジュース、モンスター、ボンク・パンチ、ビルディング・スネイク、“ハウリング”ガブ、ホンゴウ、ロックスターと一同総出でウタのいる音楽の島・エレジアに駆けつける。
名前こそ明らかになっているが、赤髪海賊団の特徴や戦闘スタイルはこれまで明かされてこなかった。谷口監督も「まず、全員のキャラクター表と名前を教えてくださいというところから入りました」と赤髪海賊団を一から知ることから始めたといい、総合プロデューサーである原作者・尾田栄一郎が描いた設定資料をもとに作り上げていった。
「このキャラクターには、実はこんな力があるということも資料には記載されていましたが、それら全部を『FILM RED』の中で見せるのは止めておきましょうということになったんです。情報過多になるのを避けたかったのはもちろん、原作漫画で彼らの能力を初披露した方がファンのみなさんも喜ぶはずです。そんなことを話しながら、彼らの活躍を調整していきました」
■荒々しさは想像以上!ルフィ&シャンクスの共闘
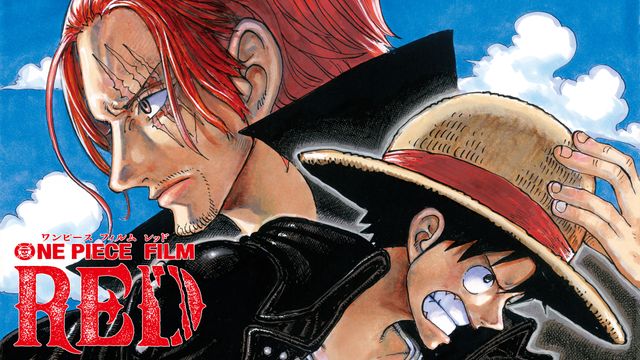
クライマックスでは、ルフィ率いる麦わらの一味と、シャンクス率いる赤髪海賊団の時空を超えた“共闘”が実現。両海賊団のメンバーが、それぞれの次元から同時攻撃を仕掛ける白熱のバトルシーンが展開する。
中でも、ルフィ&シャンクスの船長同士が繰り出す合体技は、谷口監督も納得の完成度になったという。「合体技に見える表現は私が想像していた以上に荒々しさが出ていて、良かったなと思ってます」
また、ヤソップ&ウソップ親子の“共闘”もクライマックスで実現。谷口監督は「かなり変則的な親子関係だと思います」と二人の関係性を語る。「ウソップが言っているように、親父は息子と長い間会っていませんが、息子は親父を慕っているわけですよね。恐らく、そこには一つの理想の親子関係ではなく、少し悲しみが入った関係があるのだと私は思っています。慕うか慕わないかというのは、その人次第ですから、ウソップが慕いたいと思えばそれでいいんです。誰もその気持ちを止めることはできないし、その気持ちに嘘はないわけです」
一度観ただけで終わりではなく、何度も足を運びたくなる仕掛けが詰まった本作。谷口監督は、二回目以降の鑑賞方法について「一回目で『この人中心に観たい』というのが見つかると思います。二回目は、冒頭からそのキャラクターがどのように描かれているのかを観ていただけると嬉しいです。三回目以降は、ウタ、ルフィ、ブルーノ、バルトロメオなどのそれぞれのキャラクターの視点で楽しんでいただきたい。六回目くらいで何も考えずに観られる状態になっていることが理想です」とアピール。「ストーリーを意識する必要がないというレベルに到達していただけたら、こんなに嬉しいことはありません」とファンに呼びかけた。(取材・文:編集部・倉本拓弥)


