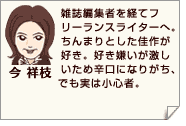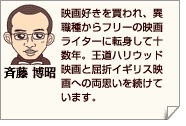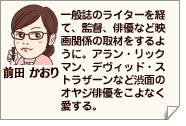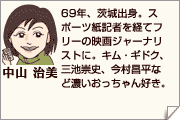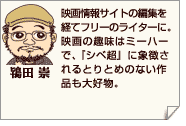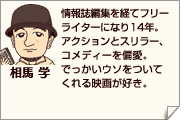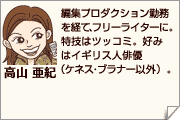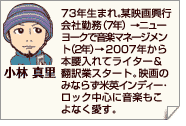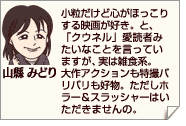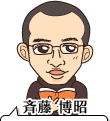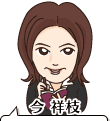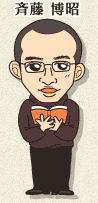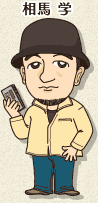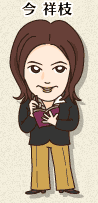サードシーズン2011年5月
私的映画宣言
『パラダイス・キス』で向井理が住む部屋が超ゴージャスなんだけど、窓からの景色がわが家のご近所なので親近感。でもこっちは築40年の古~いマンション。ロケ地の高層マンションをお城のようにうらやましく見上げる毎日です。
●5月の私的オススメ映画は、『ジャスティン・ビーバー ネヴァー・セイ・ネヴァー』(5月7日公開)。
CSで放映されていた日本劇場未公開の『レッド・ライディング』3部作を一気見。英国映画らしいダークなテイストにどっぷり浸る。DVD化希望!
●5月の私的オススメ映画は、マカロニウエスタン愛炸裂の『ファースター 怒りの銃弾』(5月21日公開)。
こんなときですが、5月はカンヌ国際映画祭へ。三池崇史監督と河瀬直美監督を同じ俎上に載せちゃうカンヌってオモロイ。これだからやめられない。
●5月のオススメは『大木家のたのしい旅行 新婚地獄篇』(5月14日公開)。竹野内豊、サイコ~!!
 ブラック・スワン
ブラック・スワン
『レスラー』のダーレン・アロノフスキー監督と、『スター・ウォーズ』シリーズのナタリー・ポートマンがタッグを組んだ心理スリラー。内気なバレリーナが大役に抜てきされたプレッシャーから少しずつ心のバランスを崩していく様子を描く。芸術監督を演じるのは、フランスを代表する俳優ヴァンサン・カッセル。主人公のライバルを、『マックス・ペイン』のミラ・クニスが熱演する。プロ顔負けのダンスシーン同様、緻密(ちみつ)な心理描写に驚嘆する。
[出演] ナタリー・ポートマン、ヴァンサン・カッセルほか
[監督] ダーレン・アロノフスキー
 本人は知的な女性なのだろうが、子役や優等生のイメージが強過ぎて、大人へのイメチェンがいつまでもできない、永遠のかわいいさん、ナタポー。それだけにこの年齢のバレリーナは彼女にしか演じられないハマり役だった。次第に追い詰められていくヒナのようなナタポーに観客のドS心さく裂。どれだけ本気で踊っているのかも話題だが、あれだけ筋肉が付けば十分では? とはいえ、まったくバレリーナ体形でないミラ・クニスも魅力的だった。
本人は知的な女性なのだろうが、子役や優等生のイメージが強過ぎて、大人へのイメチェンがいつまでもできない、永遠のかわいいさん、ナタポー。それだけにこの年齢のバレリーナは彼女にしか演じられないハマり役だった。次第に追い詰められていくヒナのようなナタポーに観客のドS心さく裂。どれだけ本気で踊っているのかも話題だが、あれだけ筋肉が付けば十分では? とはいえ、まったくバレリーナ体形でないミラ・クニスも魅力的だった。
 ナタリー・ポートマンの皮膚が「鳥肌化」した瞬間、観ていたこちらも確実に鳥肌が立った。チャイコフスキーの怒とうの音楽効果もあり、クライマックスの高揚感は異様なレベルに達し、ナタリーの恍惚(こうこつ)の表情に完ぺきノックアウト。下半身はうまく編集されていたとしても、上半身の動きだけでも十分やり遂げたでしょ、ナタリー! 観る人によって、どこまで現実なのか判断が分かれるのも本作の深み。ライバルのリリーの存在自体が幻覚というのが僕の意見です。
ナタリー・ポートマンの皮膚が「鳥肌化」した瞬間、観ていたこちらも確実に鳥肌が立った。チャイコフスキーの怒とうの音楽効果もあり、クライマックスの高揚感は異様なレベルに達し、ナタリーの恍惚(こうこつ)の表情に完ぺきノックアウト。下半身はうまく編集されていたとしても、上半身の動きだけでも十分やり遂げたでしょ、ナタリー! 観る人によって、どこまで現実なのか判断が分かれるのも本作の深み。ライバルのリリーの存在自体が幻覚というのが僕の意見です。
 主人公の胸の内で完結している心理劇だが、緊張感はホラー映画のよう。皮膚の傷や出血などの痛々しい描写はもちろん、ダンス中の足首をアップでとらえた映像も妙にグロテスク。うまく踊れない苦悩やライバルの嫉妬(しっと)、母の過保護ぶりなど、多くのプレッシャーを束ねてヒロインにぶつけてくるサディスティックな構成も、このジャンルに寄れば生きる。ナタリーのアカデミー賞受賞はバレリーナになり切った熱演への称賛というより、むしろ耐え抜いたことへのご褒美か。
主人公の胸の内で完結している心理劇だが、緊張感はホラー映画のよう。皮膚の傷や出血などの痛々しい描写はもちろん、ダンス中の足首をアップでとらえた映像も妙にグロテスク。うまく踊れない苦悩やライバルの嫉妬(しっと)、母の過保護ぶりなど、多くのプレッシャーを束ねてヒロインにぶつけてくるサディスティックな構成も、このジャンルに寄れば生きる。ナタリーのアカデミー賞受賞はバレリーナになり切った熱演への称賛というより、むしろ耐え抜いたことへのご褒美か。
 バレエしか知らないネンネちゃんが、「白鳥の湖」の黒鳥の心情を理解するために母親への反抗、クラブ遊びにレズって……コメディーなら10点満点! でもナタポーの肉体を見れば一目瞭然(りょうぜん)のマジ映画なので、頑張った彼女に免じてこの点数に。でもアカデミー賞のときに、栗山千明チャンが面白いことを言ってたな。「アロノフスキー監督は、今敏監督の『PERFECT BLUE パーフェクト ブルー』の影響を受けたのかな?」って。なるほど。千明チャンに一票。
バレエしか知らないネンネちゃんが、「白鳥の湖」の黒鳥の心情を理解するために母親への反抗、クラブ遊びにレズって……コメディーなら10点満点! でもナタポーの肉体を見れば一目瞭然(りょうぜん)のマジ映画なので、頑張った彼女に免じてこの点数に。でもアカデミー賞のときに、栗山千明チャンが面白いことを言ってたな。「アロノフスキー監督は、今敏監督の『PERFECT BLUE パーフェクト ブルー』の影響を受けたのかな?」って。なるほど。千明チャンに一票。
 プリマを目指すバレリーナの心理ドラマかと思いきや、完全なるサイコ・ホラー映画だった。が、それはそれとして全編スリリングで楽しめた。ナタリー・ポートマンがバレエシーンは「ほぼ自身で踊っている」とかいった話がどこから出てきたのかよくわからないが、それはあり得ないとしても熱演には変わりなく。しかし本作で最も素晴らしいのは、ともすれば陳腐になりそうな物語を見応えのあるエンターテインメントに仕上げたダーレン・アロノフスキーの異色の才能である。
プリマを目指すバレリーナの心理ドラマかと思いきや、完全なるサイコ・ホラー映画だった。が、それはそれとして全編スリリングで楽しめた。ナタリー・ポートマンがバレエシーンは「ほぼ自身で踊っている」とかいった話がどこから出てきたのかよくわからないが、それはあり得ないとしても熱演には変わりなく。しかし本作で最も素晴らしいのは、ともすれば陳腐になりそうな物語を見応えのあるエンターテインメントに仕上げたダーレン・アロノフスキーの異色の才能である。
 アジャストメント
アジャストメント
『マイノリティ・リポート』などの原作者フィリップ・K・ディックの短編小説を、『ボーン』シリーズのマット・デイモン主演で映画化したサスペンスアクション。第三者によって運命を支配された現実を舞台に、巨大な陰謀に立ち向かう男の奮闘を描く。監督は『ボーン・アルティメイタム』などの脚本家ジョージ・ノルフィ。主人公と愛し合うヒロインを『プラダを着た悪魔』のエミリー・ブラントが演じる。独創的かつ衝撃的な設定と予測が困難な展開に注目だ。
[出演] マット・デイモン、エミリー・ブラントほか
[監督] ジョージ・ノルフィ
 運命ならあらがえなくても、人力と知ったら、主人公でなくとも、なめてかかるだろう。しかも、その運命を動かしている人が、「MAD MEN マッドメン」では階段を上っただけで、ゲロ吐いちゃってたジョン・スラッテリーなら、なおさらだ。エミリー・ブラントの意味不明のモダンダンスといい、全編、大作らしからぬ間の抜けた、のどか感が愛おしい。見終わった後は、いろんな「もし」を妄想して、かなりの時間楽しめるので、お値ごろ感はばっちりか。
運命ならあらがえなくても、人力と知ったら、主人公でなくとも、なめてかかるだろう。しかも、その運命を動かしている人が、「MAD MEN マッドメン」では階段を上っただけで、ゲロ吐いちゃってたジョン・スラッテリーなら、なおさらだ。エミリー・ブラントの意味不明のモダンダンスといい、全編、大作らしからぬ間の抜けた、のどか感が愛おしい。見終わった後は、いろんな「もし」を妄想して、かなりの時間楽しめるので、お値ごろ感はばっちりか。
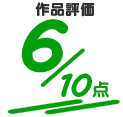 マット・デイモン、最近ちょっと出過ぎ!? そんな余計なお世話と共に、ジェイソン・ボーンの幻影がちらつく本作。究極の肉体芸でガシガシ運命調整局をぶちかます予感が、作品を素直に楽しむうえで邪魔になった気もする。ドアの使い方や時間の止め方にフリップ・K・ディックらしいSFの香りが漂いつつ、妙にラブストーリーを強調した作りも、全体の方向性をどっちつかずな印象に……。ただ、今回の役で強く確信できたのは、マットの将来。俳優辞めても政治家の活路があるよ、キミは!
マット・デイモン、最近ちょっと出過ぎ!? そんな余計なお世話と共に、ジェイソン・ボーンの幻影がちらつく本作。究極の肉体芸でガシガシ運命調整局をぶちかます予感が、作品を素直に楽しむうえで邪魔になった気もする。ドアの使い方や時間の止め方にフリップ・K・ディックらしいSFの香りが漂いつつ、妙にラブストーリーを強調した作りも、全体の方向性をどっちつかずな印象に……。ただ、今回の役で強く確信できたのは、マットの将来。俳優辞めても政治家の活路があるよ、キミは!
 ドラマの着地点がロマンチックな甘いテイストであるのは個人的な趣味とはかけ離れているが、それなりには楽しんだ。携帯電話がいきなり圏外になったり、タッチの差でバスを乗り逃がしたりなどの日常的なアクシデントの背後に「運命調整局」があるという設定は、「なるほど」と思わせるに十分。「どこでもドア」の役割を果たす帽子のアイテム的な面白さや、人間の運命を操る超人的な機関の割には妙に小役人風情な調整員たちの描写も妙味。
ドラマの着地点がロマンチックな甘いテイストであるのは個人的な趣味とはかけ離れているが、それなりには楽しんだ。携帯電話がいきなり圏外になったり、タッチの差でバスを乗り逃がしたりなどの日常的なアクシデントの背後に「運命調整局」があるという設定は、「なるほど」と思わせるに十分。「どこでもドア」の役割を果たす帽子のアイテム的な面白さや、人間の運命を操る超人的な機関の割には妙に小役人風情な調整員たちの描写も妙味。
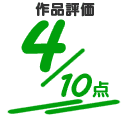 人の運命は第三者によって支配されているんだって。マット・デイモン主演で重厚な雰囲気だけど、発想的には『ファイナル・デスティネーション』と一緒。また、結局恋愛話に持っていっているところが安易。何よりこの時期に見ると、天災の犠牲になった人たちの運命も誰かに決められていたってワケ? と毒づきたくなる。福島で被災されたおばちゃんが言っていたな。「今回は天災だから、人を恨まなくていいのが幸いだ」と。本作より、おばちゃんの一言の方が深い。
人の運命は第三者によって支配されているんだって。マット・デイモン主演で重厚な雰囲気だけど、発想的には『ファイナル・デスティネーション』と一緒。また、結局恋愛話に持っていっているところが安易。何よりこの時期に見ると、天災の犠牲になった人たちの運命も誰かに決められていたってワケ? と毒づきたくなる。福島で被災されたおばちゃんが言っていたな。「今回は天災だから、人を恨まなくていいのが幸いだ」と。本作より、おばちゃんの一言の方が深い。
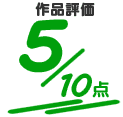 フィリップ・K・ディックの原作に「ボーン」シリーズを彷彿(ほうふつ)させる宣伝ビジュアルにつられて「SFアクション大作」を観るつもりで行くと、肩透かしの感はぬぐえないだろう。映画は運命に逆らう男女のラブストーリーにフォーカスして小さな話にまとまっている。それはそれで悪くないとは思うが、見せ方と内容のギャップは否めない。マット・デイモン&エミリー・ブラントの主演コンビも地味だが、それも含めて個人的には好印象な作品。
フィリップ・K・ディックの原作に「ボーン」シリーズを彷彿(ほうふつ)させる宣伝ビジュアルにつられて「SFアクション大作」を観るつもりで行くと、肩透かしの感はぬぐえないだろう。映画は運命に逆らう男女のラブストーリーにフォーカスして小さな話にまとまっている。それはそれで悪くないとは思うが、見せ方と内容のギャップは否めない。マット・デイモン&エミリー・ブラントの主演コンビも地味だが、それも含めて個人的には好印象な作品。
 マイ・バック・ページ
マイ・バック・ページ
海外ではベトナム戦争、国内では反戦運動や全共闘運動が激しかった1969年から1972年という時代を背景に、理想に燃える記者が左翼思想の学生と出会い、奇妙なきずなで結ばれていく社会派エンターテインメント。川本三郎がジャーナリスト時代の経験を記したノンフィクションを『リンダ リンダ リンダ』の山下敦弘監督が映像化。激動の時代を駆け抜けた若者たちの青春を初共演で体現する、妻夫木聡、松山ケンイチの熱演から目が離せない。
[出演] 妻夫木聡、松山ケンイチほか
[監督] 山下敦弘
 学生運動の話と聞くと、理解し難い壁のようなものを感じてしまうのだが、今回はそれがなかった。妻夫木や松ケンが知らない世代の若者というより、生身の人間として、ちゃんと存在していたせいだろう。妻夫木のヒーローになり切れない普通さ、松ケンのうす気味悪さ、本当に自然だった。忽那汐里の「運動ってよくわからないけど、賛成か反対かって言われると、賛成につきたくなるような気がしていた。でも、この事件はなんだか嫌な感じがする」というセリフにすべて集約されている気がする。
学生運動の話と聞くと、理解し難い壁のようなものを感じてしまうのだが、今回はそれがなかった。妻夫木や松ケンが知らない世代の若者というより、生身の人間として、ちゃんと存在していたせいだろう。妻夫木のヒーローになり切れない普通さ、松ケンのうす気味悪さ、本当に自然だった。忽那汐里の「運動ってよくわからないけど、賛成か反対かって言われると、賛成につきたくなるような気がしていた。でも、この事件はなんだか嫌な感じがする」というセリフにすべて集約されている気がする。
 妻夫木&松ケンという日本映画を牽引(けんいん)するコンビが、互いを高め合うガチ演技対決を見せてくれて爽快(そうかい)。松ケンの役は強烈さを出しやすいが、妻夫木の側は受け身の立場なので、よりハードルが高い役どころ。にもかかわらず、表情のわずかな変化や背中だけで演じたシーンに、『悪人』超えの賛辞を差し上げたい。1960年代を描きながら、マスコミ報道のあり方、冷房のない暑い夏など妙に現在の日本とシンクロするのは、偶然とはいえ、いい映画が伴う普遍性だと感じてしまった。
妻夫木&松ケンという日本映画を牽引(けんいん)するコンビが、互いを高め合うガチ演技対決を見せてくれて爽快(そうかい)。松ケンの役は強烈さを出しやすいが、妻夫木の側は受け身の立場なので、よりハードルが高い役どころ。にもかかわらず、表情のわずかな変化や背中だけで演じたシーンに、『悪人』超えの賛辞を差し上げたい。1960年代を描きながら、マスコミ報道のあり方、冷房のない暑い夏など妙に現在の日本とシンクロするのは、偶然とはいえ、いい映画が伴う普遍性だと感じてしまった。
 「自分が革命を担っている」という全共闘世代の熱気と挫折。後追い世代にも、それを体感させるに十分なリアリティー。しかし何よりの「リアル」は理想を追いかけがちな、頭でっかちの男子心理だろう。革命をうたう美辞麗句に惹(ひ)かれて足元を見失いつつ、「泣くなんて男らしくない」と、またも勝手な理想に酔う。妻夫木ふんする、そんな主人公のダメさ加減に自分を重ねてしまう男性は少なくないと思う。日本語でカバーされたディランの同名曲も味があり、グッときた。
「自分が革命を担っている」という全共闘世代の熱気と挫折。後追い世代にも、それを体感させるに十分なリアリティー。しかし何よりの「リアル」は理想を追いかけがちな、頭でっかちの男子心理だろう。革命をうたう美辞麗句に惹(ひ)かれて足元を見失いつつ、「泣くなんて男らしくない」と、またも勝手な理想に酔う。妻夫木ふんする、そんな主人公のダメさ加減に自分を重ねてしまう男性は少なくないと思う。日本語でカバーされたディランの同名曲も味があり、グッときた。
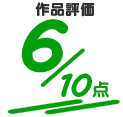 期待値が相当高かったせいもあるが、記者や仲間たちを翻弄(ほんろう)する梅山(松ケン)のキャラクターがイマイチ。松ケンが『ノルウェイの森』で演じたワタナベみたいな男だったら、記者はもちろん女子学生2人ぐらい軽~く丸め込めそうだが。山下監督の迷いが、そのまま役者の芝居に伝染したのか!? ただ雑誌編集部のシーンは超リアル。また先輩記者役の古舘寛治の異物感はたまらん。『歓待』と合わせて、本年度の助演男優賞は彼で決まり!
期待値が相当高かったせいもあるが、記者や仲間たちを翻弄(ほんろう)する梅山(松ケン)のキャラクターがイマイチ。松ケンが『ノルウェイの森』で演じたワタナベみたいな男だったら、記者はもちろん女子学生2人ぐらい軽~く丸め込めそうだが。山下監督の迷いが、そのまま役者の芝居に伝染したのか!? ただ雑誌編集部のシーンは超リアル。また先輩記者役の古舘寛治の異物感はたまらん。『歓待』と合わせて、本年度の助演男優賞は彼で決まり!
 息は詰まるような重苦しい空気に支配された1960年代末という時代を丁寧に切り取り骨太な作品に仕上がっている。とりわけ口だけは達者な革命家もどきを演じる松山ケンイチのソシオパスぶりは見事。対する妻夫木聡は残念ながら新聞社に勤める週刊誌編集部の記者としてはリアリティーに欠けるが、ラストシーンは胸にぐっときた。本作がこの時代をまったく知らない若い世代にどこまでアピールできるか、彼らがどういう感想を抱くのかが気になる。
息は詰まるような重苦しい空気に支配された1960年代末という時代を丁寧に切り取り骨太な作品に仕上がっている。とりわけ口だけは達者な革命家もどきを演じる松山ケンイチのソシオパスぶりは見事。対する妻夫木聡は残念ながら新聞社に勤める週刊誌編集部の記者としてはリアリティーに欠けるが、ラストシーンは胸にぐっときた。本作がこの時代をまったく知らない若い世代にどこまでアピールできるか、彼らがどういう感想を抱くのかが気になる。